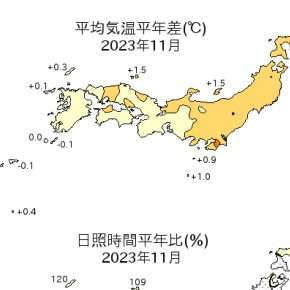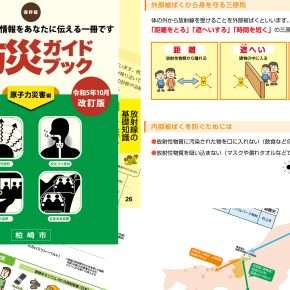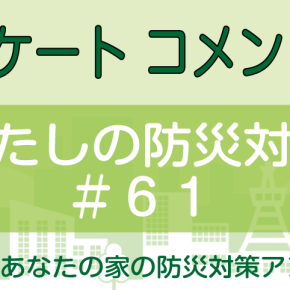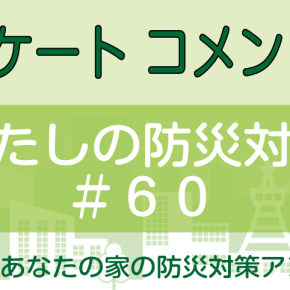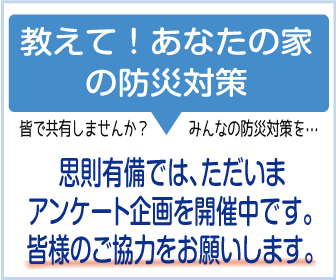![沢田正二郎の関東大震災の名言(1892~1929 / 大正期の人気俳優 劇団「新国劇」創設者・座長)[今週の防災格言746]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2022/04/c47bdf1111829263b647074dfa1bb281.jpg)
『 運命は、常に危ない分岐点を私たちに与えてその力を試そうとする。 』
沢田正二郎(1892~1929 / 大正期の人気俳優 劇団「新国劇」創設者・座長)
沢田正二郎は、関東大震災の翌月となる1923年(大正12年)10月20日に大震災直面記「難に克つ」という文を書き記している。(著書「苦闘の跡」(柳蛙書房 1928年)収録)
1923年(大正12年)8月29日の夜、浅草の公園劇場で『名月八幡祭』の公演中に新国劇座員が賭博容疑で検挙されたのを発端に、正二郎ほか新国劇所属のほとんどの座員(合計で100余名)が警察に不当勾留され拷問を受けた。「象潟事件」として知られる事件である。
浅草象潟警察署(現浅草警察署)に勾留されること三日目の9月1日朝、正二郎らは留置場から丸の内にある警視庁(日比谷赤煉瓦庁舎)へと移送された。
そこで取り調べを受けている最中に関東大地震が発生する。
四十七名の座員が、一々写真を撮られて再び調所に戻って来た丁度その時だった。何を怒ってか地殻の一角は、言い知れぬ凄い物音と共に地上のあらゆるものを震(ゆ)り倒そうとしたのだ。私は、何の予告もなく不意に生じたこの一ト震(ひとゆる)ぎに危くも横倒しに打ち倒れようとしたが、わずかに支えることが出来た時、その側には四十六名の座員が一斉に寄り集まっていた。手にはまだ例の手錠をかけられたままの身の、走ることも、逃げることもならず、危険なあの地下室の片隅に蹲(うず)くまったのだ。もしあの建物の一部でもが崩れ落ちたら、私たちは拭うべからざる汚名を着たまま、その赤煉瓦の下敷となって悲しい屍骸(むくろ)をさらさねばならぬのだった。この事件が、全く思いがけないことであったように、この大地震は、人々には、ほんとうに思いがけなかったことであろう。
やがて火の手は、警視庁の日比谷赤煉瓦庁舎(現在の丸の内・有楽町一丁目(帝国劇場の隣ビル))にも燃え移り、庁舎内部から火の手が次々にあがり、建物全体が炎上(全焼)する。

震災で炎上する警視庁(日比谷赤煉瓦庁舎)Wikimediaより
何たる運命の皮肉であろう。私はその数奇さに微笑まずにはいられなんだ。が、その微笑の直ぐ下から雨のように降りかかって来るのは、すぐ眼の前に焼け落ちる警視庁の火の粉であった。娑婆は、この大地震と大火災とでごった返している。けれども私たちは、静かに静かに、そこに蹲(うずく)まっている。 …(中略)…
家族安かれ、私の劇を愛してくれる人々安かれ、すべての人々安かれと念じ祈りつつ、私たちはまだそこに蹲くまっている。火の手がだんだん覆いかぶさって来た。彼方(かなた)此方(こなた)で、「熱ッ熱ッ」という声が聞える。
取り調べを受けていた47名の座員は縄に縛られたまま、庁舎の眼前にある皇居前広場へと避難する。
危険と見てか、係の警官は私たちを宮城前の広ッ場に連れて行ってくれた。
私たちはこの大きな異変のために、三日の間見ることの出来なかった天日の明るさを、今日漸く見ることが出来た。けれどもその陽の色は天変のために狂っていた。何事かあらねばよいがと気づかった憂いが、今その目のあたりに展開されているのだ。雑音は刻一刻とその響きを増して来る。人々の顔にもようやく不安の色が漲(みなぎ)って来る。「いよいよ世の中が壊れかかって来たのではないだろうか」と言いながら、走って通り去る者がある。それでも私たちは、幸か不幸か、まだ安らかに芝生の上に憩(いこ)うていた。
何ぞ知らん。その時すでに都の大半は、崩れかけ、燃えただれていた時なのだ。また人々は、火と煙とに囲繞(いじょう)されて、修羅の巷を叫喚していたときだったのだ。
向うから、編笠をかぶった囚人連が、幾十となくこの広場へ引き連れられて来るのをみた。これはまた、皆が皆、不安そうな面持ちで黙々として頭垂(うなだ)れている。
夕方、丸の内界隈の火の勢いはますます激しくなり、正二郎ら47名の座員はその場で全員釈放された。
やがて私は、この職を司る上の人に呼び出された。一同の顔にはある輝きの色が漲った。しかしてそれは事実となってあらわれた。
…(中略)…
命じられずとも「明日午後五時までにはふたたび集まって出頭しましょう」と約して、一同兎に角訪還(ほうかん)されることになった。それはもう、四時に近いころだった。情(なさけ)知る人々の見送りをうけながら、丸の内から一歩を外へ踏み出してみて、初めて私は、世の中の只ならぬ様に驚愕した。人は火から逃れんとして全ての財物を捨てて逃げてゆく。何という悲惨の様であろう。
正二郎らは丸の内から浅草に帰るため、迫りくる火をかいくぐりながら徒歩で進んだ。一つの判断ミスが全員の焼死につながる火の海のなか奇跡を信じた。そして、大火で昼のように明るいその夜は、皆で上野公園で過ごした。
烈風に煽られた猛火はさながら私たちを襲って来るかのようである。
裏の細道を駆ける人、も一度震(ゆ)れたらきっと崩れ落ちるにちがいない危険な屋根、しかも焔に吹きつけられて燃えしきっているその軒下を走ってゆく人、そうした焔のガードをくぐり抜け、喉が乾けば消防のホースにかぢりついて泥水で口を医(い)したり、路傍に落ちころがっている角砂糖を見つけてかぢりついたりしながら、またひた走りに須田町の方へ走って行った。萬世橋にかかろうとした時、私は、浅草と向島へ向かうに、橋を渡って上野の方へ行くべきか、右に折れて浅草橋の方から行くべきかに迷った。その時先頭に立った二三の者は既に右に折れて、「浅草橋の方へ出た方が近い」と叫んでいたが、私はそれを止めて御成街道へ渡るべく、少しは遠くともその方が安全であることを主張した。若しもあの時、浅草橋方面へ向かっていたなら、既に蔵前通りは通れなかったということだから、ただ一つ焼け落ちなかった両国橋を渡り、被服廠(ひふくしょう)の跡へでも逃げ込ませられて、あの幾万の悼(いた)ましい犠牲者たちと同じように、枕を並べて焼死したかもしれなかったのである。運命は、常に危ない分岐点を私たちに与えてその力を試そうとする。私はあるものを信じている。或る奇蹟をさえ信じている。
この信ずる力をもって、一歩々々を踏みしめながら、下町方面の火の海を恐ろしそうに見下ろしている上野山の群集を左に見ながら、車坂から真直ぐに、ここも早や火の海と化した浅草の方へ急いだ。異様に赤黒く焦げた未だに忘れることの出来ない天の色よ! この恐ろしい姿の幕は、はや夜の帳(とばり)に覆われんとしている。あらゆる電光は滅しても、燃え広がる火光によって、路面は昼のような明るさである。
…(中略)…
火を負うて逃ぐべきか、避けて逃ぐべきか。再びこの分岐点に立って考えること数分時、「自分の考え一つで、数十の人の尊い生(いのち)が危くなるのだ」この大きな責任を背負っていた私は、ここでも或る信念の閃めきを発見し得た。そうして感じたままに、私は、真暗い公園劇場の楽屋から座布団の如きものを少しづつ持ち出させ、新国劇の大提灯を列の前後に押し立て、燃え盛る火の手を側面に見ながら、二時間前に歩いた電車通を上野の山へ向かったのである。三日間、馴れぬ監房の苦しみに心身ともに痩せ細っている人々を励ましながら、漸く上野台に辿りついて振りかえれば、まず胸をつまらせるものは下町一帯の火焔である。
しかもその火の色たるや、大自然の荘厳さなどという言葉とは全然かけはなれた心憎い物凄さを帯びている。火! 火! 火の海! 満目みな火の海! むかし住んだ山の下の御徒町も、稲荷町も、初恋の思い出残るどんどん橋の付近も、芝居の閉場後、軽い疲労を覚えながら涼しい夜風に吹かれて歩いた浅草の通りも、何もかも、火と煙とに包まれてしまって、私に救いを求め叫んでいるかのような気がする。懐かしい記憶の跡々が、みんな灰になるのかと思うと、私はそれが悲しい。
焼土の帝都を生き延びた正二郎は、自分が今できる仕事と考え、無料の野外劇を企画する。
私たちは、この難に際して、先ず最初に何を為すべきであるか。
世の中の生業の中に演劇ほど、社会生活、人間生存の上に密接なる関係をもっているものはないであろう。私は、この演劇を鑑賞する人々の豊かな心持に抱かれて今日まで生長(せいちょう)して来たのである。今の私には、安住の前に奉仕がなければならぬ。私たちは、一日も早く、この荒れに荒れたる帝都に、演劇の楽園を築かねばならないことを知ったのだ。あらゆる支障を排し、あらゆる困難をくぐり、私の怨みも仇も打ち忘れて、朗らかな秋の日に、帝都幾万の人々に心の安(やす)けさを与(あた)うべく働かなければならぬ義務を感じたのだ。この企(くわだて)の為には、如何なる苦痛、如何なる恥をもしのばなければならないと思い立った。
正二郎ら新国劇は一ヵ月かけて多くの賛同者や支援者を集め、新聞各社後援、劇作家協会賛助、国民文芸会主催のもとに、10月17日から19日の三日間の野外劇「大震災罹災市民慰安野外公演」が入場無料で開催された。
『勧進帳』他の演目に、毎日数万人の市民が日比谷公園を埋め尽くした。
澤田正二郎(さわだ しょうじろう)は、大正から昭和初期に活躍した俳優。劇団「新国劇」を結成し、「沢正(さわしょう)」の愛称で親しまれた。号は柳蛙。
スピーディーで激しい殺陣(たて)を使った“剣劇(チャンバラ)”をあみだし『月形半平太』『国定忠治』などの当たり役で大衆の人気を得て、またたく間に新国劇を大劇団へと発展させたが、惜しくも36歳で急逝した。
1892年(明治25年)5月27日、税務監督官の父澤田正弘・寿々子の三人姉兄弟の末子として滋賀県大津市の三井寺(長等山園城寺)の末寺に生まれる。
父の正弘は山内家土佐藩の豪士の出身で、西南戦争(1877年)の熊本城籠城戦で活躍したが、この時の怪我がもとで1894年(明治27年)正二郎が3歳になったばかりのときに亡くなった。東京出身だった母の寿々子に連れられ一家は上京、以降は東京(下谷稲荷町、下谷御徒町など)で暮らすことになる。
下谷小学校(現・台東区立上野小学校)を経て、神田の開成中学へと進学。1908年(明治41年)、16歳のときに一高受験に失敗し、明治大学、中央大学、正則英語学校などを転々とするも勉強をせず、舞台を観たり脚本を書いたりしながら17歳で役者を志すようになった、という。
文壇や劇壇の人物の多くが早稲田大学にいることから、1909年(明治42年)に早稲田大学文科予科に入学。大学の春季大会の余興で坪内逍遙に師事し『桐一葉孤城落月』を仲間らと上演したところこれが好評となり、在学中の1911年(明治44年)に坪内逍遙が経営する文芸協会附属演劇研究所の二期生となった。1913年(大正2年)文芸協会が解散後、島村抱月、松井須磨子らの芸術座設立に参加したが、1914年(大正3年)に松井須磨子と衝突し退座。その後、新時代劇協会、近代劇協会を経て、芸術座に復帰したものの、ここでも新劇のあり方に不満を抱き、結局1917年(大正6年)に芸術座を退団し、劇団「新国劇」を旗揚げし座長を勤めた。
大阪で上演した『月形半平太』や『国定忠治』などの剣劇が大衆の絶大な支持を得、大阪での人気を背に1920年(大正9年)6月に東京進出すると、新国劇の名は沢正の愛称とともに高まることになる。
1929年(昭和4年)3月4日、中耳炎をこじらせて36歳で急逝。
日比谷野外音楽堂で行われた葬儀には10万人が集まった。
辞世の句は「何処かで囃子の声す耳の患い」。
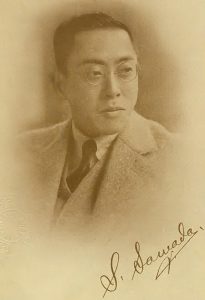
■「芸能人」「タレント」「映画人」に関連する防災格言内の主な記事
曾我廼家五九郎(1876~1940 / 喜劇俳優 大正期の「浅草の喜劇王」)(2010.06.07 防災格言)
沢田正二郎(1892~1929 / 大正期の人気俳優 劇団「新国劇」創設者・座長)(2022.04.11 防災格言)
西條八十(1892~1970 / 童謡詩人・作詞家)(2018.09.03 防災格言)
沢村貞子(1908~1996 / 女優・随筆家)(2018.01.15 防災格言)
クエンティン・クリスプ(1908~1999 / イギリスの作家・役者 ゲイカルチャーの先駆者)(2015.02.09 防災格言)
十七代目 中村勘三郎(1909~1988 / 歌舞伎役者 人間国宝(昭和50年))(2012.12.10 防災格言)黒澤明(1910~1998 / 映画監督 文化勲章・文化功労者・国民栄誉賞)(2014.02.17 防災格言)
下元勉(1917~2000 / 俳優)(2015.03.30 防災格言)
川島雄三(1918~1963 / 映画監督 代表作「幕末太陽傳(1957年)」)(2019.12.16 防災格言)
野坂昭如(1930~2015 / 作家・作詞家・歌手)(2013.02.04 防災格言)
山田洋次(1931~ / 脚本家・映画監督 代表作「男はつらいよ」)(2010.05.24 防災格言)
永六輔(1933~2016 / タレント・作家・放送作家・作詞家)(2016.07.18 防災格言)
藤本義一(1933~2012 / 小説家・放送作家・司会者)(2011.01.17 防災格言)
寺山修司(1935~1983 / 歌人・詩人・劇作家 劇団「天井桟敷」主宰)(2021.06.07 防災格言)
阿久悠(1937~2007 / 作家・作詞家)(2013.06.17 防災格言)
ジョン・レノン(1940~1980 / イギリスの歌手 “The Beatles”メンバー)(2010.12.06 防災格言)
市川森一(1941~2011 / 脚本家・劇作家・小説家)(2017.03.20 防災格言)
六代目 桂文枝(桂三枝)(1943~ / 落語家・タレント)(2015.01.19 防災格言)
つかこうへい(1948~2010 / 劇作家・演出家・小説家)(2018.03.26 防災格言)
志村けん(1950~2020 / コメディアン ザ・ドリフターズのメンバー)(2020.12.14 防災格言)
伊集院静(1950~ / 作家・作詞家)(2012.02.27 防災格言)
大森一樹(1952~ / 映画監督・脚本家 代表作『ヒポクラテスたち』)(2013.04.08 防災格言)
マイケル・ジャクソン(1958~2009 / アメリカの歌手 「ポップ界の王」)(2012.07.02 防災格言)
室井 滋(1958~ / 女優・ナレーター エッセイスト)(2013.04.01 防災格言)
宮崎美子(1958~ / 女優・タレント 熊本市出身)(2017.04.17 防災格言)
ダニエル・カール(1960~ / タレント 英語翻訳家 山形弁研究家)(2008.04.21 防災格言)
白羽弥仁(1964~ / 映画監督)(2008.01.21 防災格言)
つんく♂(1968~ / 作詞・作曲家 音楽プロデューサ―)(2019.08.19 防災格言)
クリストファー・マッカンドレス(1968~1992 / 映画「荒野へ」のモデルになったアメリカの旅人)(2014.12.15 防災格言)
■「関東大震災」に関連する防災格言内の記事
大倉喜八郎(1837~1928 / 実業家 大倉財閥の創設者 従三位男爵)(2020.08.03 防災格言)
渋沢栄一[1](1840~1931 / 幕臣 官僚・実業家・教育者 日本資本主義の父)(2013.03.18 防災格言)
渋沢栄一[2](1840~1931 / 幕臣 官僚・実業家・教育者 日本資本主義の父)(2019.07.15 防災格言)
三浦梧楼(1847~1926 / 武士・政治家 陸軍中将 子爵 号は観樹)(2015.12.21 防災格言)
南条文雄(1849~1927 / 仏教学者・真宗大谷派僧侶 日本初の文学博士)(2016.10.10 防災格言)
本山彦一(1853~1932 / 実業家・大阪毎日新聞社長 貴族院議員)(2018.05.21 防災格言)
道重信教(1856~1934 / 僧侶 増上寺法主(第79代)・浄土宗大僧正)(2018.10.22 防災格言)
名和靖(1857~1926 / 昆虫学者 名和昆虫研究所(岐阜市)の創設者)(2019.05.20 防災格言)
ミカエル・A・ステシエン(1857~1929 / 在日宣教師・ルクセンブルグの神父・キリシタン研究者)(2020.12.21 防災格言)
後藤新平(1857~1929 / 医師・官僚・政治家 関東大震災後の内務大臣兼帝都復興院総裁 ボーイスカウト日本連盟初代総長)(2010.4.26 防災格言)
内藤久寛(1859~1945 / 実業家 日本石油会社創設者・初代社長)(2014.08.18 防災格言)
市島春城(1860~1944 / 随筆家・政治家 早稲田大学初代図書館長)(2018.06.04 防災格言)
マーシャル・マーテン(1862~1949 / 横浜市ゆかりの英国人貿易商)(2014.06.23 防災格言)
山田次朗吉(1863~1930 / 剣客・直心影流第十五世 明治の剣聖)(2017.12.11 防災格言)
長岡半太郎(1865~1950 / 物理学者 東京帝国大学教授 初代大阪帝国大学総長 第1回文化勲章受章)(2021.11.22 防災格言)
平生釟三郎(1866~1945 / 実業家・教育者・政治家 甲南学園創立者 川崎造船所(現川崎重工業)社長)(2009.11.02 防災格言)
宮武外骨(1867~1955 / 明治・大正期のジャーナリスト・著述家・文化史家)(2015.08.31 防災格言)
ポール・クローデル(1868~1955 / フランスの劇作家 詩人 外交官)(2012.12.17 防災格言)
内田魯庵(1868~1929 / 評論家・翻訳家・小説家・随筆家)(2019.09.23 防災格言)
大森房吉(1868~1923 / 地震学者 東京帝国大学教授 理学博士)(2019.04.29 防災格言)
水野錬太郎(1868~1949 / 官僚・政治家 関東大震災時の内務大臣)(2016.04.11 防災格言)
井上準之助(1869~1932 / 財政家・民政党幹事長 日本銀行総裁(第9、11代)・大蔵大臣)(2018.12.03 防災格言)
小川琢治(1870~1941 / 地質学者・地理学者 京都帝国大学教授)(2019.09.09 防災格言)
佐藤善治郎(1870~1957 / 横浜市の教育者 精華小学校・神奈川学園中高等学校創立者)(2014.5.26 防災格言)
今村明恒(1870~1948 / 地震学者 東京帝国大学教授)(2008.5.12 防災格言)
佐佐木信綱(1872~1963 / 歌人・国文学者 東京帝大講師 文化勲章受章(1937年))(2021.09.06 防災格言)
武田五一(1872~1938 / 建築家・都市計画家 京大建築学科初代教授 「関西建築界の父」)(2010.6.28防災格言)
カルビン・クーリッジ(1872~1933 / 政治家 アメリカ合衆国大統領(第29~30代))(2008.5.19 防災格言)
岸上克己(1873~1962 / 社会運動家・新聞記者 埼玉県浦和町名誉助役)(2017.06.26 防災格言)
安河内麻吉(1873~1927 / 関東大震災時の神奈川県知事 内務官僚)(2008.4.28 防災格言)
二木謙三(1873~1966 / 内科医・細菌学者 駒込病院長 東京大学教授 文化勲章受章)(2016.11.14 防災格言)
山崎紫紅(1875~1939 / 明治の劇作家・詩人 歌舞伎作者)(2016.12.12 防災格言)
曾我廼家五九郎(1876~1940 / 喜劇俳優 大正期の「浅草の喜劇王」)(2010.6.7 防災格言)
天沼俊一(1876~1947 / 建築史家・古社寺修理技師・工学博士 京都大学名誉教授)(2021.09.20 防災格言)
永田秀次郎(1876~1943 / 政治家・拓務大臣 関東大震災時の東京市長)(2015.01.05 防災格言)
馬渡俊雄(1876~1946 / 内務官僚 関東大震災時の東京市助役 東京市社会局長)(2017.11.13 防災格言)
結城豊太郎(1877~1951 / 銀行家 大蔵大臣・日本銀行総裁(第15代))(2016.12.05 防災格言)
寺田寅彦[7](1878~1935 / 物理学者 随筆家 俳人)(2018.06.25 防災格言)
寺田寅彦[9](1878~1935 / 物理学者 随筆家 俳人)(2019.06.24 防災格言)
寺田寅彦[10](1878~1935 / 物理学者 随筆家 俳人)(2020.08.31 防災格言)
正宗白鳥(1879~1962 / 小説家・劇作家・評論家 文化勲章受賞)(2018.09.17 防災格言)
大正天皇(1879~1926 / 第123代天皇 諱は嘉仁(よしひと)在位1912-26)(2013.10.07 防災格言)
田中貢太郎(1880~1941 / 小説家・随筆家 代表作『日本怪談全集』)(2021.06.21 防災格言)
北澤重蔵(1880~1932 / 実業家 天津甘栗「甘栗太郎本舗」創業者)(2015.08.24 防災格言)
石原純(1881~1947 / 理論物理学者・科学ジャーナリスト 歌人)(2012.03.19 防災格言)
池田宏(1881~1939 / 都市計画家 内務官僚・内務省社会局長)(2017.10.30 防災格言)
野上俊夫(1882~1963 / 心理学者 京都帝国大学名誉教授)(2017.08.07 防災格言)
鈴木三重吉(1882~1936 / 小説家・児童文学者 日本の児童文学の父)(2011.2.21 防災格言)
大曲駒村(1882~1943 / 俳人 古川柳研究家 安田貯蓄銀行大崎支店長)(2012.08.27 防災格言)
奥谷文智(1883~1974 / 宗教家 天理教加納分教会長 機関紙「道之友」記者)(2011.11.28 防災格言)
荻原井泉水(1884~1976 / 俳人・随筆家 俳誌『層雲』を創刊)(2017.02.27 防災格言)
川村花菱(1884~1954 / 劇作家 脚本・演出家)・山村耕花(1886~1942 / 画家)(2010.2.22 防災格言)
竹久夢二(1884~1934 / 画家・詩人 美人画『黒船屋』詩『宵待草』で有名)(2012.08.20 防災格言)
加藤久米四郎(1884~1939 / 政治家・政友会 実業家 衆議院議員(7期) )(2015.10.05 防災格言)
松山基範(1884~1958 / 地球物理学者 京都大学名誉教授 山口大学初代学長)(2015.02.16 防災格言)
小寺菊子(1884~1956 / 小説家・児童文学作家 徳田秋声門下 旧姓・尾島)(2021.11.29 防災格言)
野上弥生子(1885~1985 / 小説家 法政大学女子高等学校名誉校長)(2015.06.22 防災格言)
加能作次郎(1885~1941 / 小説家 評論家 翻訳家 代表作「乳の匂い」)(2016.5.16 防災格言)
長田秀雄(1885~1949 / 詩人・劇作家 代表作『飢渇』『大仏開眼』など)(2016.10.31 防災格言)
北原白秋(1885~1942 / 詩人 童謡作家 歌人)(2014.01.06 防災格言)
谷崎潤一郎(1886~1965 / 小説家 代表作『痴人の愛』『春琴抄』『細雪』)(2014.12.08 防災格言)
岡本一平(1886~1948 / 漫画家 「元祖漫画家」「日本漫画の祖」)(2022.04.04 防災格言)
九条武子(1887~1928 / 歌人・慈善活動家 関東大震災で罹災)(2021.09.13 防災格言)
葛西善蔵(1887~1928 / 小説家 代表作『子をつれて』など)(2014.12.22 防災格言)
水上滝太郎(1887~1940 / 小説家・劇作家・実業家 代表作「大阪」)(2015.07.20 防災格言)
真野 毅(1888~1986 / 弁護士・裁判官 最高裁判所判事 第二東京弁護士会会長)(2017.09.25 防災格言)
菊池寛(1888~1948 / 小説家・劇作家 文藝春秋創業者 代表作「父帰る」)(2012.03.26 防災格言)
賀川豊彦(1888~1960 / キリスト教社会運動家・作家 イエス団創始者)(2014.10.20 防災格言)
小野蕪子(小野賢一郎)(1888~1943 / 俳人・小説家・陶芸評論家・ジャーナリスト)(2020.11.16 防災格言)
内田百閒(1889~1971 / 小説家・随筆家 代表作『冥途』『阿房列車』)(2010.3.8 防災格言)
横井弘三(1889~1965 / 洋画家)(2015.11.23 防災格言)
高橋雄豺(1889~1979 / 新聞経営者 読売新聞社主筆・読売新聞社副社長 法学博士)(2018.06.11 防災格言)
和辻哲郎(1889~1960 / 哲学者・評論家 代表作『風土』『古寺巡礼』)(2014.10.27 防災格言)
山川菊栄(1890~1980 / 婦人運動家・評論家・作家 代表作「武家の女性」)(2016.11.07 防災格言)
和辻春樹(1891~1952 / 実業家 船舶工学者・造船技師 大阪商船専務)(2013.01.21 防災格言)
土田杏村[1](1891~1934 / 哲学者・文明批評家・社会教育家 自由大学運動を推進)(2014.09.01 防災格言)
土田杏村[2](1891~1934 / 哲学者・文明批評家・社会教育家 自由大学運動を推進)(2019.10.07 防災格言)
広津和郎(1891~1968 / 小説家 文芸評論家 翻訳家 代表作『松川裁判』)(2012.07.23 防災格言)
芥川龍之介(1892~1927 / 作家・小説家)(2008.8.25 防災格言)
西條八十(1892~1970 / 童謡詩人・作詞家・仏文学者)(2018.09.03 防災格言)
堀口大學(1892~1981 / 詩人・翻訳家・フランス文学者 文化勲章受章(1979年))(2021.08.30 防災格言)
沢田正二郎(1892~1929 / 大正期の人気俳優 劇団「新国劇」創設者・座長)(2022.04.11 防災格言)
東善作(1893~1967 / 世界三大陸単独横断飛行を達成した日本の冒険家)(2010.8.30 防災格言)
松山敏(松山悦三)(1893~没不詳 / 編集者・詩人 出版社「人生社」を経営)(2018.07.30 防災格言)
林達夫(1896~1984 / 思想家・評論家・翻訳家 明治大学教授)(2012.05.21 防災格言)
大佛次郎(1897~1973 / 作家 代表作『鞍馬天狗』シリーズ)(2017.07.17 防災格言)
横光利一[1](1898~1947 / 小説家・評論家 代表作『機械(1931年)』)(2016.6.13 防災格言)
横光利一[2](1898~1947 / 小説家・評論家 代表作『機械(1931年)』)(2016.7.25 防災格言)
佐藤栄作(1901~1975 / 政治家 第61~63代内閣総理大臣)(2008.2.25 防災格言)
林芙美子(1903~1951 / 小説家 昭和初期の女流作家)(2008.4.14 防災格言)
佐多稲子(1904~1998 / 小説家 代表作『樹影』『月の宴』など)(2017.08.28 防災格言)
清水幾太郎(1907~1988 / 社会学者 ジャーナリスト 学習院大学教授)(2008.9.29 防災格言)
植草甚一(1908~1979 / エッセイスト・評論家・編集者 愛称は「J・J」)(2012.06.25 防災格言)
沢村貞子(1908~1996 / 女優・随筆家 生涯に350本以上の映画に出演)(2018.01.15 防災格言)
黒澤明(1910~1998 / 映画監督 文化勲章・文化功労者・国民栄誉賞)(2014.02.17 防災格言)
高橋浩一郎(1913~1991 / 気象学者 気象庁長官(第5代) 筑波大学教授)(2019.10.14 防災格言)
大和勇三(1914~1991 / 経済評論家 日本経済新聞社ジャーナリスト)(2010.3.29 防災格言)
渡辺文夫(1917~2012 / 実業家 東京海上火災保険会長 日本航空会長)(2013.11.25 防災格言)
池波正太郎(1923~1990 / 小説家・美食家 代表作『鬼平犯科帳』)(2012.06.18 防災格言)
吉村昭(1927~2006 / ノンフィクション作家 代表作『関東大震災』『戦艦武蔵』等)(2021.07.19 防災格言)
関東大震災(1923年)の記念碑「関東大震災十周年防災標語」(東京都銀座四丁目)(2008.7.7 防災格言)
首都直下 ホントは浅かった 佐藤比呂志教授と関東大震災(2005.10.26 店長コラム)
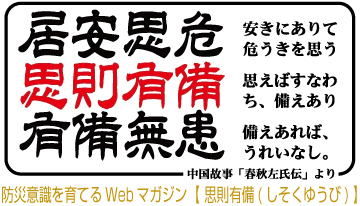





![宝永地震(1707年の南海トラフ巨大地震)の津波の石碑『宝永津波碑(徳島県海部郡海陽町鞆浦)』に遺された名言と由来 [今週の防災格言518] 宝永地震(1707年の南海トラフ巨大地震)の津波の石碑『宝永津波碑(徳島県海部郡海陽町鞆浦)』に遺された名言と由来 [今週の防災格言518]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/4079df4b53265e11c99c6e1f40b02db0-290x290.gif)
![「大変なときこそ笑え」と教える武士の修養書「葉隠(はがくれ)」の名言(山本常朝 / 1659~1719)[今週の防災格言559] 「大変なときこそ笑え」と教える武士の修養書「葉隠(はがくれ)」の名言(山本常朝 / 1659~1719)[今週の防災格言559]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2018/09/2d85247814fc59e1186393c6cc5cdd2c-234x290.png)

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)