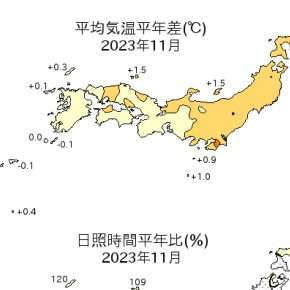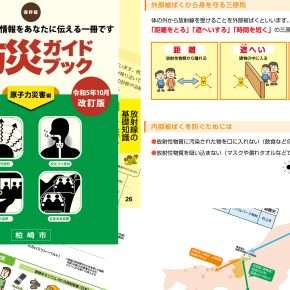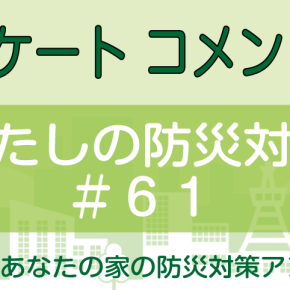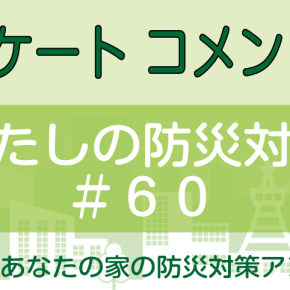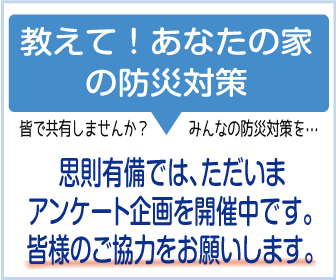![高橋浩一郎の座談会「災害にどう対処したらよいか」の名言(1913~1991 / 気象学者 気象庁長官(第5代) 筑波大学教授)[今週の防災格言616]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/e517dfdcb1247e8b4f382b2d4b105fd0.png)
『 人には、大災害はめったに起こらないという考えが根本にある。人間は横着で健忘症だから、起こらないことについ慣れてしまう。大水害や大地震があると、当座は防災対策を真剣にやるけれど、時が過ぎるとなまけていく。そうして、また大きな被害を受ける、という繰り返しがずっと続いてきた。 』
高橋浩一郎(1913~1991 / 気象学者 気象庁長官(第5代) 筑波大学教授)
格言は、1983(昭和58)年7月28日にミサワホーム主催の座談会「災害にどう対処したらよいか」(於・京王プラザホテル)より。(出典「天災人災」ミサワホーム総研出版 1984年)
曰く―――。
ひと口に災害といっても、いったい何が災害かというと、これまたややこしい。
たとえば、日本は災害国だと言います。たしかに地震があり、津波があり、台風や集中豪雨というように、災害が多いことは事実です。それが日本人の生活にいろいろ影響を及ぼしていることも事実です。しかし、それがすべて災害であるかというと疑問です。毎年決まったように来る台風は、風水害を引き起こすことが多いけれど、これは住まいや河川の防災対策が十分なされていないから災害になるのであって、もしそれがきちんとしていたら災害にはならないわけです。
かりに、台風が来ると災害になるからといって、来ないようにすると、雨が降らない。雨が降らなければ水もないということになって旱魃(かんばつ)になってしまう。これでは日本の農業はたちゆかないし、緑豊かな山河もなくなってしまう。そういう点から考えると、台風が来るということは、日本が恵まれた国であるといえるのではないか。
ですから、ひと口に災害といっても、非常に難しい。そのとらえかたと対策が問題となるのではないでしょうか。
また、いったいどこまでを災害に含めるのかですが、これも問題ですね。たとえば、災害を人間自身あるいは人間の財産の損害というように考えれば、いわゆる公害も一種の災害になる。もちろん災害の質は違うけれど、そういう見方も出来ると思います。
公害という問題は、要するに人間が増えて生産活動が上がることによって生じるわけです。生産活動が上がるということは、人間の生活を楽にすることで、プラス要素ではあるけれど、それに伴って別のマイナスが生じてしまう。こうなると”禍福は糾える縄のごとし”という感じがしますね。…(中略)…
結局、大災害というものはめったに起こらないという考えが根本にあるんじゃないでしょうか。人間は横着で健忘症なものだから、起こらないことについ慣れてしまう。大水害や大地震があると、その当座は防災対策を真剣にやるけれど、時が過ぎるとなまけていきます。そうしてまた大きな被害を受けるという繰り返しが今までずっと続いてきたんじゃないかと思うんです。だからこそ、災害の伝承、あるいは災害の歴史を調べることが重要で、それを若い世代に伝えていく必要があるわけです。
…(中略)…
最近は都市も膨張し、災害の姿そのものが変わっていますから、今までの経験をそのまま伝承してもだめで、新しい目で考えていく必要があるでしょうね。伊勢湾台風の時は堤防が破れ、高潮が襲ったわけですが、あれも「新しい人」が危険な地域に入ったために災害を大きくしている。長崎の豪雨の場合には、山の方へ入って宅地造成をしたところがやられているんです。この辺も大いに問題があると思うんです。
… … …
高橋浩一郎(たかはし こういちろう)は、天気予報や気象災害の研究で知られる気象学者。戦中から戦後の約38年にわたって気象界で活躍され、1971(昭和46)年に気象庁長官(第5代)を務めた。
1913(大正2)年5月3日、東京市下谷区(現東京都台東区)の医師で随筆家の高橋毅一郎の家に生まれる。
10歳のとき関東大震災(1923年)を飯田橋駅近くの自宅で体験。父の毅一郎が、秋田の仙北大地震(1914年 M7.1 死者94人)の教訓から「木造家屋は二階の方が安全」と叫んで、すぐさま自宅二階へ避難したという。
東京帝国大学理学部物理学科で学び、寺田寅彦や藤原咲平に師事。1936(昭和11)年、東京帝国大学理学部物理学科を卒業後、中央気象台(現気象庁)に入ると天気予報業務に携わった。1948(昭和23)年、東京帝国大学理学博士。1945(昭和20)年中央気象台予報課長、1964(昭和39)年気象研究所予報研究部長、1968(昭和43)年札幌管区気象台長、1970(昭和45)年気象庁予報部長を経て、1971(昭和46)年から1974(昭和49)年まで第5代気象庁長官に就任。
戦中には気温、風速などの量的予報の分野を開拓し、1944(昭和19)年第1回技術院賞受賞。戦後は主に長期予報の分野を開拓した。
1977(昭和52)年に気象庁を定年退官すると、1975(昭和50)年より筑波大学地球科学系教授、早稲田大学講師として後進の指導にあたり、また、日本気象協会副会長を歴任した。
日本気象学会藤原賞受賞(1969年)、第22回交通文化賞受賞(1980年)、勲二等瑞宝章受章(1983年)。
1991(平成3)年8月21日没。78歳。
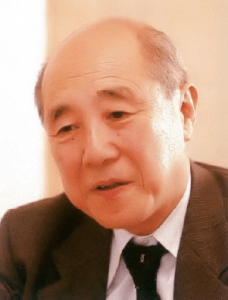
■「高橋浩一郎」に関連する防災格言内の記事
藤原咲平(気象学者 中央気象台長(第5代))(2013.10.28 防災格言)
和達清夫(物理学者 初代気象庁長官)(2007.12.03 防災格言)
圓岡平太郎(中央気象台鹿児島測候所長 口永良部島新岳噴火(1931年)報告書)(2015.06.01 防災格言
倉嶋厚(気象学者・気象キャスター 元気象庁主任予報官)(2019.07.22 防災格言)
宮澤清治(気象学者・気象キャスター)(2016.09.05 防災格言)
荒川秀俊(気象学者)(2016.10.03 防災格言)
福田矩彦(気象学者・米ユタ大学名誉教授)(2013.12.09 防災格言)
森田正光(お天気キャスター)(2017.06.05 防災格言)
寺田寅彦[1](物理学者)(2007.11.26 防災格言)
寺田寅彦[2](物理学者)(2009.03.02 防災格言)
寺田寅彦[3](物理学者)(2009.10.12 防災格言)
寺田寅彦[4](物理学者)(2011.06.20 防災格言)
寺田寅彦[5](物理学者)(2016.08.01 防災格言)
寺田寅彦[6](物理学者)(2017.08.21 防災格言)
寺田寅彦[7](物理学者)(2018.06.25 防災格言)
寺田寅彦[8](物理学者)(2019.03.11 防災格言)
寺田寅彦[9](物理学者)(2019.06.24 防災格言)
中谷宇吉郎(寺田寅彦門下の物理学者・随筆家 雪博士)(2009.10.19 防災格言)
■「洪水・水害」に関連する防災格言内の主な記事
利根川改修工事に見る水害の歴史(2010.2.26 店長コラム)
利根川の洪水想定 首都圏で死者4,500~6,300人(2010.3.5 店長コラム)
小田原評定(水俣土石流災害)(2006.1.29 店長コラム)
豪雨そして土砂災害。その犠牲者はいつも老人ホーム(2010.7.20 店長コラム)
諫早豪雨の教訓から(1957(昭和32)年7月25日)(2017.07.10 防災格言)
松野友(岐阜県本巣郡穂積町町長 日本初の女性村長)(2015.03.02 防災格言)
及川舜一(元岩手県一関市市町 カスリーン台風とアイオン台風の大水害)(2015.09.14 防災格言)
小川竹二(元新潟県豊栄市長 下越水害)(2017.09.11 防災格言)
奥貫友山(利根川・荒川水害である寛保大水害時の慈善家)(2010.4.5 防災格言)
川合茂(河川工学者 舞鶴工業高等専門学校名誉教授)(2011.08.15 防災格言)
高橋裕(河川工学者 東京大学名誉教授)(2017.06.12 防災格言)
幸田文(随筆家・小説家 代表作『崩れ』『流れる』)(2015.05.11 防災格言)
桑原幹根(愛知県知事)(2014.09.15 防災格言)
廣井悠 (都市工学者)(2012.03.12 防災格言)
大隈重信 (佐賀藩士・早稲田大学創立者)(2010.09.27 防災格言)
下田歌子 (歌人・実践女子学園創始者)(2009.12.14 防災格言)
平生釟三郎 (川崎重工業社長)(2009.11.02 防災格言)
山下重民 (明治のジャーナリスト 風俗画報編集長)(2008.09.22 防災格言)
吉田茂 (政治家)(2008.05.05 防災格言)
脇水鉄五郎(地質学者・日本地質学会会長)(2011.07.18 防災格言)
谷崎潤一郎 (作家)(2014.12.08 防災格言)
矢野顕子 (シンガーソングライター ハリケーン・サンディ水害)(2016.10.17 防災格言)
森田正光 (お天気キャスター)(2017.06.05 防災格言)
中央防災会議「大規模水害対策に関する専門調査会」(2008年9月8日)より(2018.07.09 防災格言)
二宮尊徳翁(二宮金次郎)(江戸時代後期の経世家・農政家)(2012.01.30 防災格言)
上杉鷹山 (江戸時代中期の大名 出羽国米沢藩9代藩主)(2010.04.12 防災格言)
莅戸善政[1] (かてもの作者 出羽国米沢藩家老)(2008.03.17 防災格言)
莅戸善政[2] (かてもの作者 出羽国米沢藩家老)(2011.12.05 防災格言)
中江藤樹 (江戸時代初期の陽明学者 近江聖人)(2010.11.22 防災格言)
『百姓伝記』(1680~1682年・著者不明)巻七「防水集」より(2018.08.27 防災格言)
中西 進(国文学者 大阪女子大名誉教授 文化勲章受章)(2019.04.08 防災格言)
寺田寅彦[9](物理学者 室戸台風直後の随筆から)(2019.06.24 防災格言)
藤原咲平 (気象学者 室戸台風後の著書『天気と気候』より)(2013.10.28 防災格言)
丹羽安喜子(歌人 室戸台風で罹災)(2016.08.22 防災格言)
倉嶋厚(気象学者・お天気キャスター 元気象庁主任予報官)(2019.07.22 防災格言)
高橋浩一郎(気象学者 気象庁長官(第5代) 筑波大学教授)(2019.10.14 防災格言)
| – Amazon.co.jp – | ||||
|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|
防災格言,格言集,名言集,格言,名言,諺,哲学,思想,人生,癒し,豆知識,防災,災害,火事,震災,地震,備蓄,防災グッズ,非常食
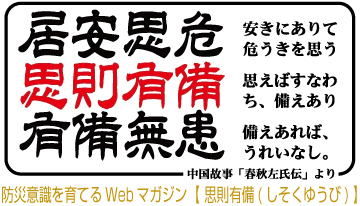
![関東大震災の時にアメリカで日本救援を呼び掛けた東善作が遺した格言(冒険家)[今週の防災格言146] 関東大震災の時にアメリカで日本救援を呼び掛けた東善作が遺した格言(冒険家)[今週の防災格言146]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/bousaikakugen-290x290.jpg)
![坂本竜馬が兄にあてた手紙に書き記した名言(1836~1867 / 幕末の尊皇派の志士 土佐藩郷士)[今週の防災格言409] 坂本竜馬が兄にあてた手紙に書き記した名言(1836~1867 / 幕末の尊皇派の志士 土佐藩郷士)[今週の防災格言409]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/218.png)
![遠藤周作(1923~1996 / 小説家・随筆家)の随筆「心の操縦法」の名言 [今週の防災格言695] 遠藤周作(1923~1996 / 小説家・随筆家)の随筆「心の操縦法」の名言 [今週の防災格言695]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2010/07/1ef2a1f33c6e775b7c4febb6fc53caf8-290x289.png)
![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)