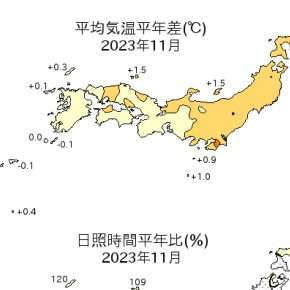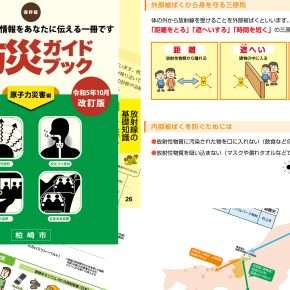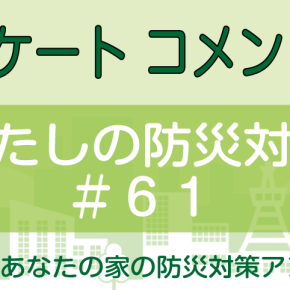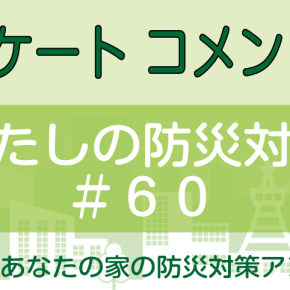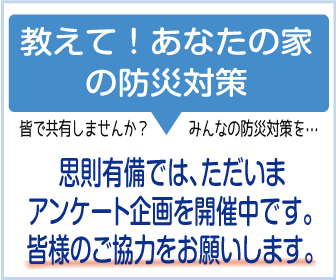![真鍋淑郎(米国の気象学者 ノーベル物理学賞(2021年))博士の国際気象学大気物理学協会(IAMAP)講演「温暖化に伴う大気・海洋結合系の数世紀に亘る変動」(1993年)の名言 [今週の防災格言721]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/68f7bb87b73e6f2006817afd8d47f0a5.jpg)
『 4倍増の実験(二酸化炭素濃度が現状維持ペースで上昇する)で起きたような非常に大きい気候の永年的変化が起らない、とは限らない。 』
真鍋淑郎(1931~ / 米国の気象学者 米プリンストン大学上席研究員 ノーベル物理学賞(2021年))
二酸化炭素濃度の上昇が地球温暖化に影響するという予測モデルにより、炭酸ガスが現状維持のペースで増加した場合(4倍増の実験)、500年後の全球平均気温上昇は7℃に達し、海面水準の上昇は1.8mに及ぶという。
格言は、1993年(平成5年)7月11日~23日にパシフィコ横浜で開催された国際気象学大気物理学協会(IAMAP)科学会議内の基調講演「温暖化に伴う大気・海洋結合系の数世紀に亘る変動 ( Greenhouse Gas−Induced Evolution of the Coupled Ocean−Atmosphere−Land Surface System over Several Centuries )」より。(日本気象学会機関紙「天気 vol.40, IAMAP・IAHS ’93 特集号」(1994 年3月31日)掲載)
曰く―――。
炭酸ガスが増加すると、地球の平均温度の永年的上昇を通じて海洋大気の結合システムの大規模現象が影響を受け、気候が大きく変わるので、その効果は非常に重大である。たとえば、海洋の熱塩循環が大きく変わる可能性がある。
氷期の終わりころ、温度上昇と氷床融解にともなって海洋循環が突然変わったらしいというBroeckerの議論(1987年)も、その可能性を示唆する。ここでは、海洋大気結合気候モデルを用いて、炭酸ガス量の2倍ないし4倍増加による全球気候の数100年間の変動を計算した。
結論的には、500年後の全球平均気温上昇は、炭酸ガス2倍増の場合は3.5度、4倍増の場合は7度に達する。また、海水の熱膨張による海面水準の上昇はそれぞれ1mと1.8mに及ぶことがわかった(氷床の融解が加わると、海面上昇はこれよりさらに大きい)。さらに、炭酸ガス4倍増の時は、海洋の温度構造や力学構造が著しく変わる。
すなわち、海洋の熱塩循環はぱったり止み、温度躍層がぐっと下がる、というまったく新しい安定な状態に落ち着いてしまう。
このような変化は海洋深層との物質の交換を阻害するので、大気海洋結合系の炭素循環や生物地球科学過程に大きな影響を及ぼす可能性がある。…(中略)…
年間1%の割合(IPCCによるBAU(※business-as-usual=現状維持)の上昇率)で炭酸ガスの増加する4XCの最初の140年では、全球平均にして、気温上昇率は1世紀につき約3.5度である。これは、IPCCがBAU炭酸ガス増加率を仮定して見積もった、1世紀につき3度という値より、若干大きめである。
このモデルの炭酸ガス2倍増に対する平衡応答の結果は約3.5度で、IPCCの推定している気候感度の範囲の1.5~4.5度の上半分に属する。ゆえに、現モデルは実際の気候より感度が高いかもしれない。IPCCによると、BAUの上昇率で温室効果ガスの放出が21世紀の末まで続くと炭酸ガス4倍増に相当する温室効果が実現するという。炭酸ガスが4倍増することを防止するために、ドラコ流の厳しい規制(※ドラコ流(Draconian)とは古代アテネの執政官 Dracon(ドラコン)から派生した言葉で、厳格で厳しい、苛酷なという意味)がおそらく必要となるであろう(Walker et al.,1992)。
現モデルが気候感度を過大評価している可能性を考慮すると、2XCと4XCの実験(※炭酸ガスの時間的変化を仮定した結合モデルの500年積分計算)は将来の気候変化の可能範囲を示している、と推測するのが妥当だろう。
4XC実験(※炭酸ガスが毎年1%の割合で増加(1990年のIPCCのBAU増加率に近い割合)すると仮定)で起きたような非常に大きい気候の永年的変化が起らない、とは限らない。
… … …
眞鍋淑郎(まなべ しゅくろう)博士は、気象予測を行うコンピューターモデルの先駆者の一人で、地球温暖化の研究・予測の理論的基礎を確立したことにより、2021年に気象分野初となるノーベル賞(物理学)を受賞した人物。
特に、大気中の温室効果ガスの増加に伴う気温上昇を数値予測することに初めて成功し、大気の流れと海洋大循環とを組合わせた「大気海洋大循環モデル」を発表し、地球温暖化現象における海洋の役割を明らかにしたことで知られる。
1931年(昭和6年)9月21日、愛媛県宇摩郡新立村(現・四国中央市新宮町)出身。祖父の代から村内唯一の医院だった家に生まれる。
新宮尋常高等小学校、旧制愛媛県立三島中学校(現・愛媛県立三島高等学校)を経て、東京大学理学部地球物理学科に入学。地球物理学教室の正野重方(1911~1969)に師事し、1958年(昭和33年)に東京大学大学院博士課程を修了、「凝結現象の綜観的研究」で理学博士。
東大時代の「雨の数値予報」の論文が、後の米海洋大気局(NOAA)地球物理流体力学研究所(GFDL)初代所長ジョセフ・スマゴリンスキー(Joseph Smagorinsky 1924~2005)の目に留まり研究所に招請された。1958年(昭和33年)渡米し米国立気象局(NWS)に研究員として入局。後に主任研究員となり、1968年(昭和43年)よりプリンストン大学客員教授を兼任。1975年(昭和50年)米国市民権(国籍)を取得。
1997年(平成9年)日本へ一時帰国し、宇宙開発事業団と海洋科学技術センターによる政府系共同プロジェクト「地球フロンティア研究システム」で地球温暖化予測のプログラムディレクターに就任するが、2001年(平成13年)ディレクターを辞任し、米国へと戻り、海洋大気局(NOAA)地球流体力学研究所(GFDL)上級研究員、プリンストン大学大気海洋科学プログラム上級研究員などを歴任。
主な受賞歴に、日本気象学会「藤原賞」(1966年)、ベンジャミン・フランクリン・メダル(2015年)、クラフォード賞(2018年)、ノーベル物理学賞(2021年)など。

photo by Bengt Nyman, Crafoord Prize EM1B0732; Crafoord Prize 2018, Geosciences, Kungliga Vetenskapsakademien, Syukuro Manabe and Susan Solomon, via flickr.com.
■「気象学者」に関連する防災格言内の記事
藤原咲平(1884~1950 / 気象学者 中央気象台長(第5代))(2013.10.28 防災格言)
和達清夫(1902~1995 / 物理学者 初代気象庁長官)(2007.12.03 防災格言)
圓岡平太郎(中央気象台鹿児島測候所長 口永良部島新岳噴火(1931年)報告書)(2015.06.01 防災格言
倉嶋厚(1924~2017 / 気象学者・気象キャスター 元気象庁主任予報官)(2019.07.22 防災格言)
宮澤清治(1923~2011 / 気象学者・気象キャスター 気象庁天気相談所長)(2016.09.05 防災格言)
荒川秀俊(1907~1984 / 気象学者・災害史家 元気象庁気象研究所長)(2016.10.03 防災格言)
福田矩彦(1931~2010 / 気象学者 米ユタ大学名誉教授 米気象学会特別会員)(2013.12.09 防災格言)
森田正光(1950~ / お天気キャスター (株)ウェザーマップ代表取締役)(2017.06.05 防災格言)
中谷宇吉郎[1](1900~1962 / 寺田寅彦門下の物理学者・随筆家 「流言蜚語(1945年)」より)(2009.10.19 防災格言)
中谷宇吉郎[2](1900~1962 / 寺田寅彦門下の物理学者・随筆家 「水害の話(1947年)」より)(2020.07.06 防災格言)
立春の日のコロンブスの卵(中谷宇吉郎随筆より)(2006.01.17 編集長コラム)
高橋浩一郎(1913~1991 / 気象学者 気象庁長官(第5代) 筑波大学教授)(2019.10.14 防災格言)
真鍋淑郎(1931~ / 米国の気象学者 米プリンストン大学上席研究員 ノーベル物理学賞(2021年))(2021.10.18 防災格言)
■「地球環境問題」に関連する防災格言内の記事
真鍋淑郎(1931~ / 米国の気象学者 米プリンストン大学上席研究員 ノーベル物理学賞(2021年))(2021.10.18 防災格言)
ミハイル・ゴルバチョフ (旧ソビエト連邦最後の共産党書記長)(2008.03.24 防災格言)
コフィー・アナン(国連事務総長(第7代) ノーベル平和賞受賞)(2018.10.08 防災格言)
ワンガリ・マータイ(ケニアの環境保護活動家 ノーベル平和賞)(2013.04.22 防災格言)
ロバート・ボッシュ(1861~1942 / ドイツの実業家 自動車部品メーカー・ロバート・ボッシュの創立者)(2011.12.12 防災格言)
ヘルムート・トリブッチ (ドイツの自然科学者「動物は地震を予知する」の著者)(2011.10.24 防災格言)
ドナルド・ディングウェル(ドイツの火山学者)(2011.02.07 防災格言)
ギュンター・グラス(ドイツのノーベル賞作家)(2015.04.20 防災格言)
マイケル・ポーラン(ジャーナリスト カリフォルニア大学教授)(2012.09.10 防災格言)
リチャード・ウィルソン(物理学者 ハーバード大学名誉教授)(2015.9.28 防災格言)
今井通子(登山家・医師 東京農業大学客員教授)(2010.02.01 防災格言)
田部井淳子(1939~2016 / 登山家 女性初のエベレスト・七大陸最高峰登頂者)(2019.12.23 防災格言)
岡崎洋(元神奈川県知事)(2009.08.10 防災格言)
伊藤和明(元NHK解説委員)(2009.7.20 防災格言)
明石康(元国連事務次長・NPO日本紛争予防センター会長)(2009.03.30防災格言)
村上処直(都市防災家)(2009.12.07 防災格言)
立松和平(作家)(2010.02.15 防災格言)
手塚治虫[1] (漫画家・医学博士 代表作「ブラック・ジャック」)(2013.09.30 防災格言)
手塚治虫[2](漫画家・医学博士 漫画の神様)(2020.10.05 防災格言)
宇田道隆(海洋物理学者)(2017.08.14 防災格言)
松永安左エ門 (実業家)(2012.08.13 防災格言)
高橋裕(河川工学者 東京大学名誉教授)(2017.06.12 防災格言)
下河辺淳(建設官僚・都市計画家国土庁事務次官)(2018.04.23防災格言)
野中広務(政治家・衆議院議員)(2018.02.12 防災格言)
■「ノーベル賞」に関連する防災格言内の記事
アンリ・デュナン(1828~1910 / スイスの事業家 赤十字社の創設者 ノーベル平和賞(1901年))(2011.05.02 防災格言)
ラビンドラナート・タゴール(1861~1941 / インドの詩人 思想家 小説家 ノーベル文学賞(1913年))(2011.05.30 防災格言)
マクファーレン・バーネット(1899~1985 / オーストラリアの免疫学者 ノーベル生理学・医学賞)(2020.02.03 防災格言)
佐藤栄作(1901~1975 / 政治家・内閣総理大臣 ノーベル平和賞(1974年))(2008.2.25 防災格言)
朝永振一郎(1906~1979 / 物理学者 文化勲章(1952年) ノーベル物理学賞(1965年) )(2021.04.12 防災格言)
江崎玲於奈(1925~ / 横浜薬科大学学長 ノーベル物理学賞(1973年) 文化勲章)(2018.03.19 防災格言)
ギュンター・グラス(1927~2015 / ドイツの作家 ノーベル文学賞)(2015.04.20 防災格言)
ミハイル・ゴルバチョフ(1931~2022 / ソビエト連邦最後の共産党書記長 ノーベル平和賞(1990年))(2008.03.24 防災格言)
真鍋淑郎(1931~ / 米国の気象学者 米プリンストン大学上席研究員 ノーベル物理学賞(2021年))(2021.10.18 防災格言)
コフィー・アナン(1938~2018 / 国連事務総長(第7代) ノーベル平和賞(2001年))(2018.10.08 防災格言)
ワンガリ・マータイ(1940~2011 / ケニアの環境保護活動家 ノーベル平和賞(2004年))(2013.04.22 防災格言)
ラルフ・スタインマン(1943~2011 / カナダの免疫学者 ノーベル生理学・医学賞受賞)(2011.10.10 防災格言)
ポール・クルーグマン(1953~ / アメリカの経済学者・コラムニスト ノーベル経済学賞(2008年))(2021.01.11 防災格言)
ロバート・ベーデンパウエル(1857~1941 / スカウト運動提唱者)(2008.05.26 防災格言)
大森房吉(1868~1923 / 地震学者 東京帝国大学教授 理学博士)(2019.04.29 防災格言)
賀川豊彦(1888~1960 / キリスト教社会運動家)(2014.10.20 防災格言)
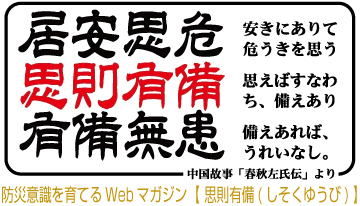







![猪瀬直樹が東日本大震災の時に残した格言(作家・元東京都知事)[今週の防災格言495] 猪瀬直樹が東日本大震災の時に残した格言(作家・元東京都知事)[今週の防災格言495]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/3b4cb966a0320e2722498c2ef7a68c10.png)
![野坂昭如が司馬遼太郎との対談「日本の土地と農民について」述べた食糧備蓄の名言(1930〜2015 / 作家)[今週の防災格言269] 野坂昭如が司馬遼太郎との対談「日本の土地と農民について」述べた食糧備蓄の名言(1930〜2015 / 作家)[今週の防災格言269]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/4c50d0477a7e020031aaa63f67799d7e-290x290.jpg)
![松岡俊三の『雪害第二建白書』の名言(1880〜1955 / 豪雪地帯救済に一生を捧げた政治家)[今週の防災格言423] 松岡俊三の『雪害第二建白書』の名言(1880〜1955 / 豪雪地帯救済に一生を捧げた政治家)[今週の防災格言423]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/232-273x290.png)
![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)