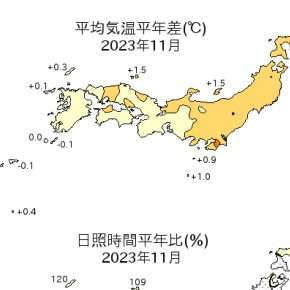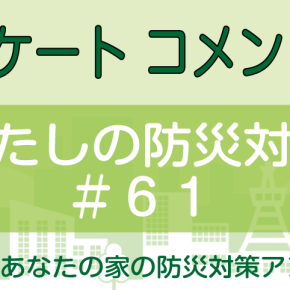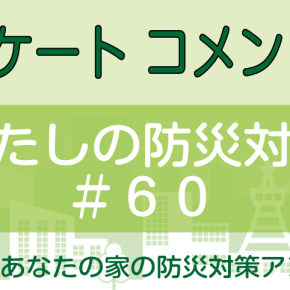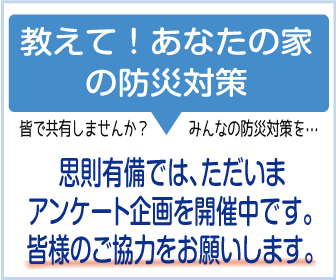![西村秀一医師(1955~ / 国立病院機構仙台医療センター・ウイルスセンター長)の随筆「パンデミックの本当の怖さとは、そしてリスクの冷静な評価と適切なリスクコミュニケーションの必要性について」からの名言 [今週の防災格言649]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/bousaikakugen.jpg)
『 本当に必要なのは自分たちの地域は自分たちで守るという自覚である。 』
西村秀一(1955~ / ウイルス学者・医師 仙台医療センターウイルスセンター長)
格言は、アルフレッド・W・クロスビー著、西村秀一翻訳『史上最悪のインフルエンザ』(みすず書房 2004年)から。
新型インフルエンザ騒動下の2008(平成20)年12月に本書が新装増版された際に、西村秀一氏が巻末に寄稿した『パンデミックの本当の怖さとは、そしてリスクの冷静な評価と適切なリスクコミュニケーションの必要性について』(2008年12月)より。
曰く―――。
《 本書(A・W・クロスビー著「史上最悪のインフルエンザ」)、序文には次のような一節がある。
概して我々は、死亡率は低いが早晩自分たちが関わることになるはずの現実的な病気より、自分たちがほとんど罹りそうにもない高い死亡率を持つ病気の方にずっと恐怖を抱くものである。
スパニッシュ・インフルエンザの被害は、本書でわかるように相当なものだったが、統計上は、意外にも流行全体を通した患者あたりの致死率は2%あたりに落ち着くとされる。この致死率2%という数値は、先の鳥インフルエンザのそれとくらべてはるかに低い数字である。だが、実はこちらの方がずっと危険であることに思い至るべきである。
インフルエンザの怖さは、一度に大勢の人たちが感染することにほかならない。だから死亡率がそこそこ低くとも、絶対数として大勢の人たちの命が犠牲となったり、社会生活が大混乱したりするのである。
我々がいうパンデミック対策とは、あくまでこれを何とかしようとするものである。減災(mitigation)という考え方がある。災害は不可避としても、そのなかで被害をできるだけ抑える工夫をすることだが、対策の究極の目標はこれでなくてはならない。
・・・《中略》・・・
私見を述べさせてもらえるとしたら、キーワードは「個々の地域の現場の対策」である。繰り返すがインフルエンザ・パンデミックの難しさは各地域社会に一時的に極めて多くの患者が出ることである。地域の行政と医療は、予想される膨大な数の患者を前に何ができるか。何をやらなければならないか。地域住民には何が求められ、何ができるか。
当時、対策の中心は、まさしく「人」であった。危機に遭って誰かが立ち上がり、自分たちができることを考え実行した地域があった。これこそ我々が本書から学ぶべき点である。ノウハウがないと嘆く「市町村」は、とかく国や県などお上に頼りがちである。資金も何もないと嘆いてそれで終わりであれば、それは他人事である。だが、本当に必要なのは自分たちの地域は自分たちで守るという自覚である。いきなり全国共通の理想的形だけを追い求めれば、それはないものねだりに等しい。自分たちの実情にあわせ、背伸びしすぎない、地域に根ざした生活者としての視点で考えることが必要なのである。みな同じお仕着せをねだるのではなく、いわば身の丈にあった仕立てを自分たちでやるのである。我々はできることしかできないのだ。やれることとやれないことが見えてくれば腹が据わるというものである。そして、ここがスタートである。おんぶに抱っこでは何も始まらないし、始まったとしても形だけで終わってしまう。
その一方で、国の役割だが、パンデミックに際して国は地域に対して個別の(オーダーメイドの)具体的支援はできない。全体に対して、参考にしてもらうガイドラインを出すくらいでしかない。国や県のやるべきこと、あるいはやれることは地域の活動の活性化を促すような取り組みをおこない、市町村が動きやすいような調整役に徹することではなかろうか。そして、そうやってやる気を起こした地域の自主性を重んじることである。少なくとも、自分たちに合った独自の動きをしようとする地域を、規則でがんじがらめにしないことであり、あとは、できるかぎりそのための資金援助をすることである。
・・・《中略》・・・
ある人がパンデミック対策は「釜の飯を炊くような仕事をしなくてはいけない」と言ったとき、訳者(西村秀一)はすかさず、このままでは真っ黒焦げのご飯になってしまうと返したものである。国民の関心、あるいは少なくとも行政の関心が、今後適正レベルで維持されていくことを望むばかりである。
著者が日本語序文で紹介してくれている寺田寅彦の「ものを怖がらなすぎたり怖がりすぎたりするのはやさしいが、正当に怖がることはなかなかむつかしい」という言葉の持つ意味を、今こそ噛みしめるべきときではないだろうか。(2008年12月) 》
西村秀一(にしむら ひでかず)医師は、呼吸器系ウイルス感染症を専門とするウイルス学者。研究医として仙台市宮城野区にある独立行政法人「国立病院機構仙台医療センター」臨床研究部病因研究室長・ウイルスセンター長を務める。医学博士。
1955(昭和30)年、薬剤師の父のもと山形県新庄市に生まれる。山形県立山形東高等学校を経て、1984(昭和59)年山形大学医学部医学科を卒業。山形大学医学部細菌学教室助手を経て、1994(平成6)年から全米研究評議会(National Research Council=NRC)のフェローとして、米国ジョージア州アトランタにある米国疾病制御予防センター(CDC)のインフルエンザ部門に留学。後に同部門客員研究員。1996(平成8)年に帰国後、国立感染症研究所ウイルス一部主任研究官を経て、2000(平成12)年より現職。主な訳書にリチャード・E・ニュースタット/ハーヴェイ・V・ファインバーグ著『豚インフルエンザ事件と政策決断─1976 起きなかった大流行』(時事通信出版局 2009年)、デイビッド・ゲッツ著『インフルエンザ感染爆発』(金の星社 2005年)。絵本の翻訳に、メイヒュー「ケイティ」シリーズ、コーワン「ヒッポ先生」シリーズ(いずれもサイエンティスト社)がある。
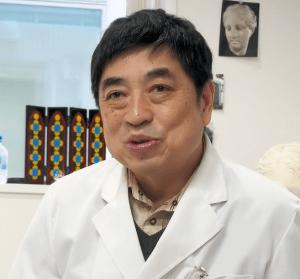
■「西村秀一」「ウイルス学者」に関連する防災格言内の記事
寺田寅彦「ものをこわがらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがることはなかなか難しい」(2009.3.2 防災格言)
アルフレッド・W・クロスビー(アメリカの歴史学者 「史上最悪のインフルエンザ」著者)(2014.07.28 防災格言)
日沼頼夫(ウイルス学者 京都大学名誉教授 塩野義製薬副社長)(2020.01.27 防災格言)
ラリー・ブリリアント(1944~ / アメリカ合衆国の免疫学者・医者・慈善活動家)(2020.05.25 防災格言)
マクファーレン・バーネット(オーストラリアの免疫学者 ノーベル生理学・医学賞)(2020.02.03 防災格言)
尾身茂(医師 名誉WHO西太平洋地域事務局長 自治医科大学名誉教授)(2020.03.02 防災格言)
竹田美文(医学者 国立感染症研究所長)(2009.05.04 防災格言)
岡部信彦(小児科医 国立感染症研究所感染症情報センター長)(2009.02.23 防災格言)
遠藤周作[2](作家・随筆家 文化勲章受章)(2018.11.19 防災格言)
下村海南(下村宏)[2](肺結核について 官僚政治家・歌人)(2020.04.13 防災格言)
与謝野晶子(歌人 スペイン風邪についての随筆)(2020.03.23 防災格言)
柳瀬実次郎(小児科医 大阪回生病院長 大阪こども研究会発起人)(2014.09.08 防災格言)
田尻稲次郎[1](法学者 スペイン風邪当時の東京市長・専修大学創立者)(2008.12.22 防災格言)
田尻稲次郎[2](法学者 スペイン風邪当時の東京市長・専修大学創立者)(2008.12.29 防災格言)
マーガレット・チャン(第7代WHO事務局長)(2009.05.01 編集長コラム)
テドロス・アダノム(第8代WHO事務局長)(2020.03.16 防災格言)
李文亮(中国・武漢市中心医院の眼科医 新型肺炎で最初に警告を発した医師)(2020.02.17 防災格言)
厚生労働省 2007(平成19)年 インフルエンザ総合対策標語(2009.10.26 防災格言)
CDC(米国疾病予防管理センター)感染対策ガイドライン(2013.12.30 防災格言)
ガレノス(古代ローマ帝国の医者・哲学者)(2020.02.24 防災格言)
バルダッサーレ・ボナイウティ(フィレンツェの歴史家)(2020.02.10 防災格言)
ジョヴァンニ・ボッカチオ(フィレンツェの詩人・散文作家 「デカメロン」著者)(2010.11.15 防災格言)
村上陽一郎(科学史家 東京大学名誉教授「ペスト大流行」より)(2015.06.29 防災格言)
川崎富作(小児科医 川崎病を発見)(2009.01.05 防災格言)
北里柴三郎(細菌学者 医学者)(2008.12.15 防災格言)
二木謙三 (内科医・細菌学者)(2016.11.14 防災格言)
吉益東洞(1702~1773 / 江戸時代の漢方医 日本近代医学中興の祖)(2020.05.11 防災格言)
大隈重信 (佐賀藩士・早稲田大学創立者)(2010.09.27 防災格言)
渋沢栄一[1] (幕臣・日本資本主義の父)(2013.03.18 防災格言)
渋沢栄一[2](幕臣 官僚・実業家・教育者 日本資本主義の父)(2019.07.15 防災格言)
後藤新平 (政治家)(2010.4.26 防災格言)
ウイリアム・ハスラー(アメリカの予防医学者 サンフランシスコ市の衛生官としてスペイン風邪パンデミック対策を主導した人物)(2020.06.22 防災格言)
フランシス・ラッセル(アメリカの郷土史家 ボストンのスペイン風邪についての伝記より)(2020.04.06 防災格言)
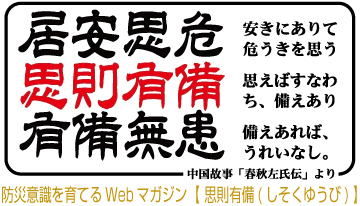


![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)