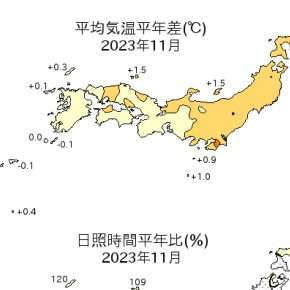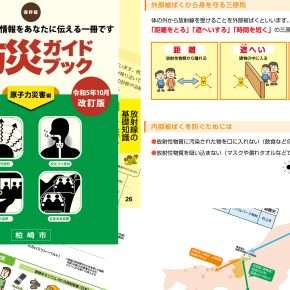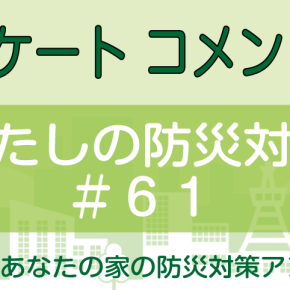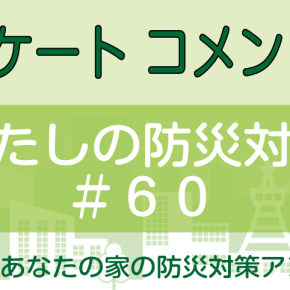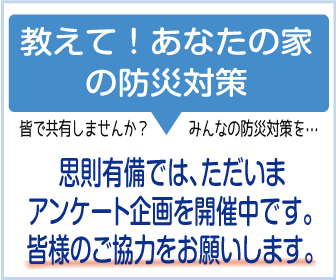![鴨長明が「方丈記」に記した健康・養生など生活信条の名言(1155~1216 / 平安時代末期の歌人・随筆家)[今週の防災格言643]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2020/04/0e15d1daee690ac3f1cb792669cc8571.png)
『 身 、心 の苦 しみを知 れれば、苦 しむ時 は休 めつ、まめなれば、使 ふ。いかにいはんや、常 に歩 き、常 に働 くは、養性 なるべし。 』
鴨長明(1155~1216 / 平安時代末期の歌人・随筆家 代表作『方丈記』)
口語訳『 身体は、心がその疲労の程度を把握しているので、疲れたときは休ませ、元気なときは働かせる。言うまでもなく、こまめに歩き、こまめに体を動かすのは健康の増進にもいいはずだ。』
曰く―――。
身 、心 の苦 しみを知 れれば、苦 しむ時 は休 めつ、まめなれば、使 ふ。使 ふとても、たびたび過 ぐさず。もの憂 しとても、心 を動 かすことなし。
いかにいはんや、常 に歩 き、常 に働 くは、養性 なるべし。なんぞ、いたづらに休 み居 らん。人 を悩 ます、罪業 なり。いかが、他 の力 を借 るべき。口語訳: 身体は、心がその疲労の程度を把握しているので、疲れたときは休ませ、元気なときは働かせる。働かせるといっても、度を過ごすことはない。身体がだるくて怠けても、いらいらする必要はない。心が体を管理しているからだ。
言うまでもなく、こまめに歩き、こまめに体を動かすのは健康の増進にもいいはずだ。どうしてだらだらと体を動かさないでいいことがあろう。体は動かすに限る。しかも、使用人を雇って苦労を押しつける のは、罪作りの行為にほかならない。どうして他人の力を借りていいことがあろう。何事も自分でするに限る。
(訳文:武田友宏編「方丈記(全)」(角川ソフィア文庫 平成19年))
方丈記が書かれた時代は、源平の合戦の頃、武家社会へと価値観が大きく変わり、天変地異が次々と起こる不安な時代であった。
京都の名門「下鴨神社」の神官の子として将来を約束された鴨長明は、ついにはその座に就くことなく山里の小さな庵(方丈庵)に隠棲し、この世の無常を綴った。
方丈記は、鴨長明が58歳のときの随筆で、若いころに京都で体験した大火、辻風、福原遷都、飢饉、地震という五つの災厄を「世の不思議」として描いた災害文学として知られる。

■「方丈記」に関連する防災格言内の記事
鴨長明[1](平安時代末期の歌人・随筆家 代表作『方丈記』)(2008.03.31 防災格言)
鴨長明[2](平安時代末期の歌人・随筆家 代表作『方丈記』)(2012.05.28 防災格言)
鴨長明[3](平安時代末期の歌人・随筆家 代表作『方丈記』)(2020.04.20 防災格言)
兼好法師(吉田兼好)[1](『徒然草』第211段より)(2010.01.04 防災格言)
兼好法師(吉田兼好)[2](『徒然草』第73段より)(2012.06.04 防災格言)
■「養生」「健康」に関連する防災格言内の記事
ウォルター・B・キャノン(アメリカの生理学者 動物の恒常性(ホメオスタシス)を提唱)(2020.03.30 防災格言)
エイブラム・カーディナー(心的外傷後ストレス障害(PTSD)を定義した米国の精神科医)(2019.01.21 防災格言)
フランシス・ラッセル(アメリカの伝記作家・歴史家・郷土史家)(2020.04.06 防災格言)
田村康二(医師 山梨大学医学部名誉教授)(2012.10.22防災格言)
中井久夫(精神科医 神戸大学名誉教授 文化功労者)(2020.03.09 防災格言)
勝海舟 (従五位下・安房守)(2012.12.03 防災格言)
賀川豊彦(キリスト教社会運動家)(2014.10.20 防災格言)
■「鎌倉時代」「平安時代」に関連する防災格言内の記事
鴨長明「人のいとなみ、皆愚なる中に、さしも危うき京中の家を造るとて、宝を費やし、心を悩ますことは、すぐれてあぢきなくぞ侍る」(2012.05.28 防災格言)
鴨長明「恐れの中に恐るべかりけるは、ただ地震(なゐ)なりけりとこそおぼえ侍(はべ)りしか。」(2008.03.31 防災格言)
兼好法師『徒然草』「よろづの事は頼むべからず。愚かなる人は、深く物を頼むゆゑに、恨み怒ることあり」(2010.01.04 防災格言)
吉田兼好『徒然草』「世に語り伝ふる事、
北畠親房「人民の安からぬ事は時の災難なれば、神も力及ばせ給はぬにや」(『神皇正統記』より)(2015.06.08 防災格言)
北畠親房「少しの事も心に許す所あれば、大きに誤る本となる」(『神皇正統記』より)(2014.04.14 防災格言)
源為憲「もろもろの物の中に捨てがたきはおのが身より過ぎたるはなし。」(『三宝絵詞』より)(2018.03.05 防災格言)
「人間はこれ生死無常、芭蕉泡沫のさかひ」(『保元物語』より)(2015.03.23 防災格言)
楠木正成「事に臨んで恐れ、
「ただ、悲しかりけるは大地震なり。鳥にあらざれば空をも翔りがたく、竜にあらざれば雲にも又上りがたし」(『平家物語』巻十二より)(2014.02.10 防災格言)
「する事かたきにあらず、よくする事のかたきなり。」(『十訓抄』より)(2018.07.02 防災格言)
慈円 (鎌倉時代の天台宗僧侶)(2014.03.17 防災格言)
無住(鎌倉時代の臨済宗僧侶)(2014.08.25 防災格言)
「更に今日の命、物食はずは生くべからず。後の千の
「昨日は他人の
藤原敦光「安くして危きを忘れざるは、古の炯誡なり」(2011.09.05 防災格言)
「眠たいは大事のことぞ」(『平家物語』より)(2013.01.16 店長コラム)
防災格言,格言集,名言集,格言,名言,諺,哲学,思想,人生,癒し,豆知識,防災,災害,火事,震災,地震,備蓄,防災グッズ,非常食
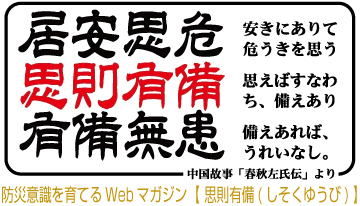
![大谷圭一が雑誌『週刊新潮』で語った格言(元・防災科学技術研究所防災総合研究部長)[今週の防災格言167] 大谷圭一が雑誌『週刊新潮』で語った格言(元・防災科学技術研究所防災総合研究部長)[今週の防災格言167]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/bousaikakugen-290x290.jpg)
![寺田寅彦が遺したといわれる『 天災は忘れた頃来る』その出どころは?[今週の防災格言100] 寺田寅彦が遺したといわれる『 天災は忘れた頃来る』その出どころは?[今週の防災格言100]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2020/08/ae656bfd79d465d11938265e1faa086a-290x290.png)
![荒川秀俊が著書『実録大江戸壊滅の日』に記した格言(気象学者)[今週の防災格言459] 荒川秀俊が著書『実録大江戸壊滅の日』に記した格言(気象学者)[今週の防災格言459]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/1878c3440524818443bb70f4efee655b-290x290.png)
![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)