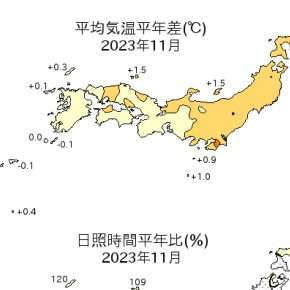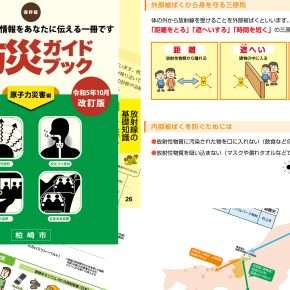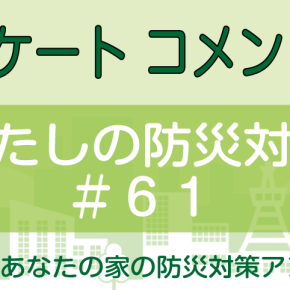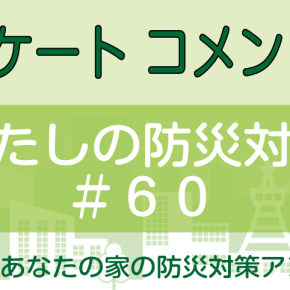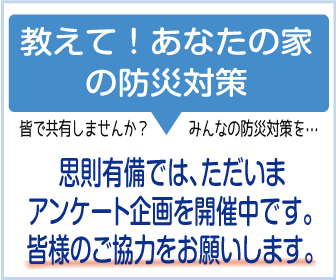![岡村正吉(1922~2010 / 北海道虻田郡虻田町長)が洞爺湖温泉街を襲った有珠山噴火(1977年)災害時に述べた名言 [今週の防災格言240]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/bousaikakugen.jpg)
『 噴火というものは、風上と風下とでは、まさに天国と地獄の差がある 』
岡村正吉(1922~2010 / 北海道虻田郡虻田町長)
北海道の観光リゾート地である洞爺湖温泉街を襲った昭和52(1977)年8月の有珠山大噴火で、災害の陣頭指揮をとり早期復興への道を切り拓いた人物の一人が、北海道虻田(あぶた)町出身の岡村正吉(おかむら まさよし)氏である。
岡村氏は、東京大学法学部を卒業後に北海道庁に入庁。水産部、広報課長、北海道教育長を歴任し退任。昭和47(1972)年に衆院選出馬を表明するも断念、昭和49(1974)年6月、故郷虻田町(現洞爺湖町)の町長選に初当選し、平成10(1998)年に落選するまで虻田町長を6期24年務めた。
在任中の昭和52(1977)年8月7日に有珠山が突然大噴火し、噴煙は上空12,000メートルに達し、火山灰は遠く知床半島まで降り積り、火山礫は洞爺湖温泉街を直撃、雨を含んだ火山灰が泥流となって洞爺村まで押し寄せ3人の住民が犠牲となった。災害対応に虻田町長としてリーダーシップを発揮、積極的な中央への陳情を行うなど高い行政手腕により壊滅的な被害を受けた町の早期復興を実現させ、その後のハザードマップ整備にも力を入れた。
平成22(2010)年10月2日札幌市の病院で死去。88歳。
格言は自著『噴火災害にはじめて遭って』(出典:全国防災協会編「語り継ぐ災害の体験(山海堂 1981年)」集録)より。
曰く―――
『 生れて初めて空からバラバラと降ってくる火山礫を見たとき、私たちはみんな外に飛び出して、ワイワイいいながらわれ先に珍しい火山礫を拾った。しかし、間もなく歓声は、悲鳴に変わっていった。
降灰礫はさらにどんどん続いた。そして雨になった。雨混じりの火山灰は、空から生コンが降ってくるようなものだった。車という車は、みんなフロントガラスをやられ使えなくなっていた。<中略>道路という道路は、30センチから1メートルも生コンが積って途絶状態だった。
それにしても、除灰とは除雪の何倍も困難なものである。大体、重量が違うし、ドロドロで雪のようにあっさりしていない。それでも日ごろ除雪の経験体制があったから迅速な除灰も可能なのだった。
それにしても、八日、一晩中は住民は生きた気もしなかったろう。バラバラとしじゅう火山礫が降りつづき、中には屋根を貫通してくるものもある。私たちは、避難命令を出すにも出せない。道路が通れなかったからだ。』
■「岡村正吉」に関連する防災格言内の記事
寺田寅彦(1935年の浅間山噴火)の名言「正しく怖がる」(2009.03.02 防災格言)
大プリニウス(AD23~AD79 / 古代ローマ帝国の博物学者・政治家・軍人)(2021.03.15 防災格言)
小プリニウス(AD61~AD112 / 古代ローマ帝国の文人・政治家)(2009.07.01 防災格言)
イタリア トーレ・デル・グレコ市モットー(Torre del Greco’s motto)(2013.03.11 防災格言)
チャールズ・ダーウィン(1809~1882 / イギリスの自然科学者)(2014.04.21 防災格言)
ポール・クローデル(1868~1955 / フランスの劇作家 詩人 外交官)(2012.12.17 防災格言)
幸田文(1904~1990 / 小説家・随筆家 幸田露伴の次女 富士山の「崩れ」の名言)(2015.05.11 防災格言)
水上武(1909~1985 / 火山物理学者・理学博士 東京大学名誉教授)(2014.10.13 防災格言)
岡村正吉(1922~2010 / 1977年有珠山噴火時の北海道虻田郡虻田町長)(2012.07.16 防災格言)
下鶴大輔(1924~2014 / 火山学者 火山噴火予知連会長 東京大学名誉教授)(2015.08.10 防災格言)
三島由紀夫(1925~1970 / 作家 『床の間には富士山を―私がいまおそれているもの(1965年)』の名言)(2014.07.07 防災格言)
圓岡平太郎 (中央気象台鹿児島測候所 口永良部島新岳噴火(1931年)報告書)(2015.06.01 防災格言)
石原慎太郎(1932~ / 小説家・政治家・東京都知事)(2013.07.22 防災格言)
津村建四朗(1933~ / 地震学者 元地震調査推進本部地震調査委員会委員長)(2013.07.08 防災格言)
大竹政和(1939~ / 地震学者 東北大学名誉教授 第4代地震予知連会長)(2014.01.13 防災格言)
『富士山噴火と東海大地震』(木村政昭(琉球大学名誉教授)監修、著者・安恒理(ジャーナリスト)ほか 2001年)「被災時のサバイバルとは」より(2021.11.08 防災格言)
岡田弘(1943~ / 地球物理学者 専門は火山学 北海道大学名誉教授)(2014.09.29 防災格言)
池谷浩(1943~ / 元建設省砂防部長 砂防地すべり技術センター理事長)(2009.08.03 防災格言)
藤井敏嗣(1946~ / 火山学者 東大地震研究所教授 火山噴火予知連会長)(2010.04.19 防災格言)
都司嘉宣(1947~ / 地震学者・専門は地震考古学 理学博士 元東京大学地震研究所准教授)(2013.03.25 防災格言)
立松和平(1947~2010 / 小説家 浅間山噴火の小説「浅間」より)(2010.02.15 防災格言)
菊地正幸(1948~2003 / 地震学者 東京大学教授 リアルタイム地震学を提唱)(2009.11.16 防災格言)
山岡耕春(1958~ / 地震学者 名古屋大学教授 地震火山・防災研究センター長)(2012.04.23 防災格言)
ドナルド・ディングウェル(1958~ / ドイツの火山学者・地球物理学者 ミュンヘン大教授)(2011.02.07 防災格言)
気象庁(2001年7月4日 火山噴火予知連絡会 富士山ワーキンググループ発表より)(2011.01.31 防災格言)
霧島山・新燃岳火山噴火(2011年)を考える(2011.01.28 店長コラム)
防災格言,格言集,名言集,格言,名言,諺,哲学,思想,人生,癒し,豆知識,防災,災害,火事,震災,地震,危機管理,非常食
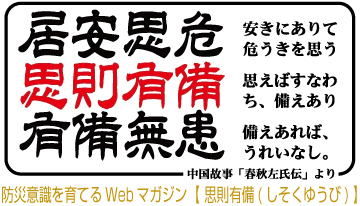
![中島湘煙が新聞『自由燈(じゆうのともしび)』に記した名言(1863~1901 / 女性解放運動家 フェリス女学院名誉教授)[今週の防災格言189] 中島湘煙が新聞『自由燈(じゆうのともしび)』に記した名言(1863~1901 / 女性解放運動家 フェリス女学院名誉教授)[今週の防災格言189]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/a778f6730718557eb9dcb8211d7b8d12-290x290.png)
![荒川秀俊が著書『実録大江戸壊滅の日』に記した格言(気象学者)[今週の防災格言459] 荒川秀俊が著書『実録大江戸壊滅の日』に記した格言(気象学者)[今週の防災格言459]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/1878c3440524818443bb70f4efee655b-290x290.png)
![下鶴大輔(1924〜2014 / 火山学者 火山噴火予知連会長 東京大学名誉教授)が国会・災害対策特別委員会(1974年)で遺した名言 [今週の防災格言399] 下鶴大輔(1924〜2014 / 火山学者 火山噴火予知連会長 東京大学名誉教授)が国会・災害対策特別委員会(1974年)で遺した名言 [今週の防災格言399]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/bousaikakugen-290x290.jpg)
![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)