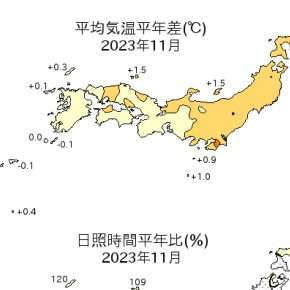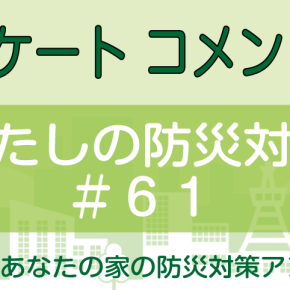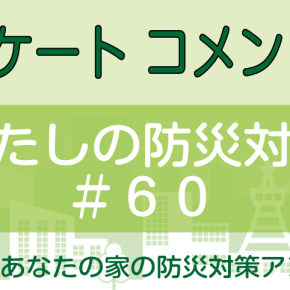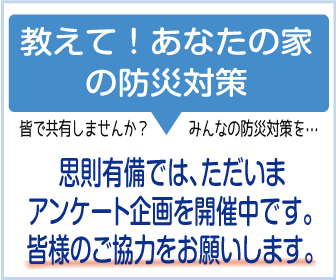様々な情報を収集し、分析し、評価し、今後の予測に活かすインテリジェンス(諜報活動・情報活動)は、主に国家の安全保障分野や政治・経済の国際間の駆け引きで今も活用されています。今から約80年前の太平洋戦中に大本営情報参謀(陸軍少佐)だった堀栄三氏の回顧録『 大本営参謀の情報戦記~情報なき国家の悲劇~ 』は、大戦中に日本軍が情報面で何をやっていたかを中心に、敗戦までのエピソードを交えて教訓を語った歴史的名著として知られています。秋山進氏のシリーズ連載「リスクの本棚」の第七回では、本書を取り上げていただきました。
連載・リスクの本棚~リスクに関わる名著とともに考える~vol.7
堀栄三『 大本営参謀の情報戦記~情報なき国家の悲劇~ 』(1989年)
情報途絶と意思決定時のバイアスについての必読書
リスクは多様である。自然災害など外部かつ直接の制御が不可能なリスクから、内部事象で本来は制御可能なはずのリスクまで数限りない。今回は顕在化すると組織にとって致命的となる“情報途絶リスクと意思決定のバイアス”に関する名著をご紹介したい。
 大本営参謀の情報戦記 ―情報なき国家の悲劇― (文春文庫) |
「大本営参謀の情報戦記」は、太平洋戦争時の情報参謀であり、戦後は自衛隊統幕情報室長を務めたインテリジェンスのプロである堀栄三氏による戦中の回顧録である。戦場がどんな状況にあり、そこにどんな指示が大本営からもたらされ、その大きなギャップの中で、どのように現場の将校が考え、行動したか、これらを“情報の獲得と解釈”という観点から記述したものである。
本書の最終章に米軍が1946年に出した「日本陸海軍の情報部について」という調査書についての記載があり、著者は「あまりにも的を射た指摘に、ただ脱帽あるのみである。」と評している。
具体的には
-
(1) 軍部の指導者は、ドイツが勝つと断定し、連合国の生産力、士気、弱点に関する見積もりを不当に過小評価してしまった。( 国力判断の誤り* )
-
(2) 不運な戦況、特に航空偵察の失敗は、最も確度の高い大量の情報を逃がす結果となった。( 制空権の喪失* )
-
(3) 陸海軍の円滑な連絡が欠けて、せっかく情報を入手しても、それを役立てることが出来なかった。( 組織の不統一* )
-
(4) 情報関係のポストに人材を得なかった。このことは、情報に含まれている重大な背後事情を見抜く力の不足となって現れ、情報任務が日本軍では第二次的任務に過ぎない結果となって現れた。( 作戦第一、情報軽視* )
-
(5) 日本軍の精神主義が情報活動を阻害する作用をした。軍の立案者たちは、いずれも神がかり的な日本不滅論を繰り返し声明し、戦争を効果的に行うために最も必要な諸準備を蔑ろにして、ただ攻撃あるのみを過大に強調した。その結果彼らは敵に関する情報に盲目になってしまった。( 精神主義の誇張* )
の5つのポイントである。
実際、本書において著者が主張している日本軍部の情報に関する問題点はこの5点に集約されているといえるだろう。
(1) 国力判断の誤り
陸軍の大本営第二部(情報部)は、各国の軍備の状況にくわえ政情や経済力などについての分析を行う部署である。著者は陸軍大学校を卒業したのち、この第二部に配属される。情報部は、長年の仮想敵国であるソ連の情報収集に対しては積極的だったものの、米英に対して特別の準備はされておらず、米英情報を収集する班が課に昇格したのは、なんと太平洋戦争開戦後の約半年後だったというから驚かざるを得ない。また、本来は相手国の事情に精通した人を情勢判断や意思決定時に重用すべきところを、
「返す返すも米国通といわれた人びとが、中央部から疎外されて、権力者に都合のよい者たちだけが中央の要職を占めたのは残念極まることであった」
と言うほどであった。まったく相手を知らず、知ろうという努力をすることなく、戦争に突入し、戦争を遂行していたということになる。
(2) 制空権の喪失
「百二十年昔のクラウゼヴィッツの時代でさえも、戦場で制高点を占領することが、戦争の要諦だと戦争論で述べている。そこへ飛行機が出現した。クラウゼヴィッツの制高点を飛行機という文明の技術で作ろう、米国はそう考えた。制高点の人工的創造である。それには制空権をもって、これを維持することだ、そうすれば飛行機で山が作れる。」
「誰でも戦術を習った者は、制空権を口にする。制空権がなければ、軍艦も輸送船も動けない。輸送船が動かなくては、燃料も弾薬もやってこない。・・・なぜ日本は制空権を喪ったか、『軍の主兵は航空なり』これを事前に採用しなかったからだ。」
情報戦において、高い位置からすべてを見通すことができる部隊と、現場からの情報しかない部隊では、状況の把握において隔絶たる差が出る。制空権が得られないものは、大局観のある情報も得られず、軍艦も支援に来ず、補給もできず、相手に対して劣後するのみである。戦争のパラダイムが飛行機の出現で大きく変わってしまったことをまったく理解できていなかったのである。
(3) 組織の不統一
帝国陸軍と帝国海軍の対立は有名で、互いに張り合い、情報の円滑な交換がなされなかった。それどころか著者は、
「陸軍の中でも作戦部、情報部、技術本部、航空本部などがまったくバラバラの活動をしていた。」
という。
実際にはまったく戦果がなかったにもかかわらず、多数の戦艦や空母を撃沈したという海軍の台湾沖航空戦のデタラメ大戦果発表を鵜呑みにした陸軍が、急遽作戦変更して、レイテ決戦を行い、そして大失敗に終わるといったように偽情報にお互いが踊らされた。
「一般国民から見れば、大本営とは一つであったはずだが、内では陸軍と海軍がお互いに真相も打ちあけることはなく、二つの大本営が存在していたのである。」
いわずもがなではあるが、国力が勝る相手にこれでは勝ちようもない。
(4) 作成第一、情報軽視
大本営というのはエリートの入るところだが、そのなかでも作戦課、さらに作戦班は、陸大の軍刀組(成績優秀者)しか入れないところであった。一方、情報部は人材を得ておらず、また作戦課は情報部の判断を重要なものとはまったく考えていなかった。著者は、大本営の中にも別格参謀と一般参謀があった、と述べている。過去の成功事例を学習し、机上演習で良い成績を上げた現場をほとんど知らない“別格参謀”の間違った指示によって大きな失敗がもたらされたという。
また、情報部は情報部で、配属以降も、特別な教育が施されたわけではなかった。著者は独自の研鑽によって分析能力を高め、数々の米軍の行動の予測に成功して名を馳せたのであった。
本国帰任の際に、第十四方面軍の山下泰文司令官に挨拶をした。そのとき、
「お前は本当によくやってくれた。お前のような専門家をこのまま比島の山の中におらせることはできない。戦争はまだまだ続く。日本に帰って本土決戦のために、もっともっと働いてくれ、日本はお前を待っているのだ。山下個人の慾でお前をここに置くわけにはいかないのだ」
という言葉をもらい涙をこぼす。しかしながら、「お前のような専門家」が本当はたった1年2か月の経験しかない新米ホヤホヤであり、そのような者が対米情報の専門家になってしまうこと自体が、日本の情報分析のお粗末な実態であることを強く感じたという。
(5) 精神主義の誇張
これについては面白い記述がなされている。
「海軍は海という一面平坦で隠れることの出来ない水面を戦場として、自分の大砲の口径が何インチであり、相手の大砲は何インチであるから、その飛距離からどちらかの勝ち、と勝敗は敵とはかなり離れたところで数字的に決められる。したがって、米国の戦力と自軍の戦力とを戦う前に計算してしまう。よほどの悪天候や、夜戦でもない限りこの数字をひっくり返すことはできないと考えるようになる。ところが陸軍は、桶狭間の戦いに代表されるように、兵力の多い方が必ず勝つとは限らない。夜暗も、濃霧も、知隙も、森林も、山岳もある。利用すべきものは全部利用して、奇襲で成功した例は、近代戦の中にもたくさんある。勢い必勝の信念こそが第一で、兵力の多寡や兵器の優劣ではないという教育になりやすい。・・・・ 海軍は数字を見て早く諦めるが、陸軍は少々のことでは諦めないで最後までやる。」
しかし、「しょせん、戦略の失敗を戦術や戦闘でひっくり返すことはできなかったということである」と結ぶ。当たり前のことだが、圧倒席な物量と情報量の差を前にしては、局地戦における戦術の良さや不屈の精神力だけではどうにもならないのである。
さて、この書からわれわれは何を学べるであろうか。
第一には「情報獲得の重要性」である。制空権に相当するもの、それはユーザーやお客様企業の嗜好や行動のデータということになろう。それを保有している企業と、それを保有できていない企業。保有しようと投資している企業とそれさえもしない企業。ここで大きな差が出てくることは間違いがない。
第二には「情勢判断への継続的努力」の必要性であろう。社会がどのような方向に向かうのか、競合はどのように立ち向かってくるのか。想定していた敵国がソ連から米英に変わったとき、陸軍はとっさに対応しなかった。いまは別領域から新しい競合が越境して入ってくる時代である。真珠湾攻撃から半年たって初めて米英課を作った陸軍を笑うことは簡単だが、同じようなことがあなたの会社でも起こっているかもしれない。
第三には、「情報将校の育成」である。情報判断の必要性は理解したとしても、それを実践できる優秀な人材がいなくては情報の分析はできない。たった1年2か月で専門家と呼ばれるようになった陸軍と同じようなことが起こっていないだろうか。ちなみに、軍組織においては、“敵情報を集めて分析する人”と“作戦を練る人”は別人がやることになっている。なぜならば、作戦者が情報獲得と分析をすると、自分のやりたい作戦実行にむけて、感情や期待が入ることで情報の判断を間違えることが往々にしてあるからとのことである。
第四には、組織間の連携である。陸軍内の連携を妨げたものは、明治以降の藩閥対立や予算獲得競争などによって、互いが “仮想敵国よりも目障りな敵” になってしまった歴史的経緯がある。残念なことに、会社組織の中においても同様な構図はよく見られる。社会的変化や外敵の動向に合わせて、柔軟に組織を組み替え、情報の分断や協調の意志の低下を防がなくてはならない。第二次大戦時において、英、米、独、ソ、仏などの列強ではすでに空軍が独立していたにも関わらず、日本だけが陸軍航空と海軍航空とにわかれて統合空軍にならないまま戦争に突入したことが本書では紹介されている。当時、陸軍からも海軍からもその必要性を認める声があったにも関わらず、統合空軍設立に立ちはだかったのが、実は真珠湾の航空戦で大戦果をあげたはずの山本五十六海軍大将であったことを本書は示唆している。状況に応じ、個別最適化ではなく全体最適化を図れるような組織と情報の流れを作り出していくことは大変重要である。
そして最後に、「戦略の策定」である。核たる戦略をもたず昨日の延長戦上でのみ明日を考えることはどの組織でも起こっていることである。日本陸軍にあっては、中国大陸での戦闘で得た体験知が強く、その計算尺で米英との戦闘を測ろうとしていた。そうした傾向は参謀や隊長のように指導層に入る人々の間に強かったという。過去、強くない相手と戦った経験をもとに、異なる技術と戦略を持つ相手との闘いを判断しようとすることで、あらゆる点で不適切な結果を導いたのである。DX時代にあって、これから多くの会社が直面するのは、まさにこのような問題であろう。経営者や参謀的な立場の人間の使っている思考の道具がすでに時代遅れになっているかもしれない。
著者は、孫子の言葉を引用して情報獲得、情報分析の重要性を述べる。
「爵禄百金を惜しんで、敵の情を知らざるは不仁の至なり、人の将にあらざるなり、主の佐にあらざるなり、勝の主にあらざるなり」
これは、敵情を知るには人材や金銭を惜しんではいけない。これを惜しむような人間は将帥でもなく、幕僚でもなく、勝利の主になることは出来ないという意味である。そして情報を収集するには、最優秀の人材とあり余る金を使えと教えている。きわめて至言と思われるが、実際のところ、みなさんの会社では情報のために人とお金をかけているであろうか? 私は寡聞にして、そのような会社の例をあまり聞いたことがない。
評者:秋山 進(あきやま・すすむ)

1963年、奈良県生まれ。京都大学経済学部卒。リクルート入社後、事業企画に携わる。独立後、経営・組織コンサルタントとして、各種業界のトップ企業など様々な団体のCEO補佐、事業構造改革、経営理念の策定などの業務に従事。現在は、経営リスク診断をベースに、組織設計、事業継続計画、コンプライアンス、サーベイ開発、エグゼクティブコーチング、人材育成などを提供するプリンシプル・コンサルティング・グループの代表を務める。国際大学GLOCOM客員研究員。麹町アカデミア学頭。
主な著書に『「一体感」が会社を潰す』(PHP研究所)、『それでも不祥事は起こる』『転職後、最初の1年にやるべきこと』(日本能率協会マネジメントセンター)、『社長!それは「法律」問題です』(日本経済新聞出版)などがある。
【関連リンク】
・プリンシプル・コンサルティング・グループ:https://www.principlegr.com/
・麹町アカデミア:http://k-academia.co.jp/
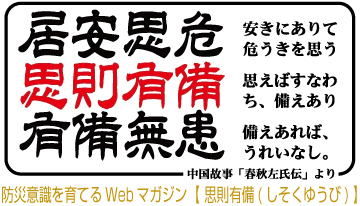







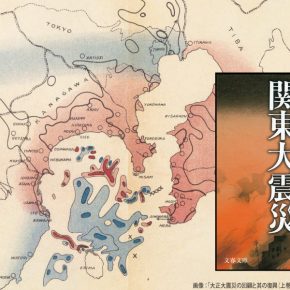












![竹内政明(1955〜 / ジャーナリスト 読売新聞東京本社取締役論説委員)が読売新聞「編集手帳」に残した名言 [今週の防災格言511] 竹内政明(1955〜 / ジャーナリスト 読売新聞東京本社取締役論説委員)が読売新聞「編集手帳」に残した名言 [今週の防災格言511]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/1ab21f2490be39eee1f7c2a78998a137-290x290.png)
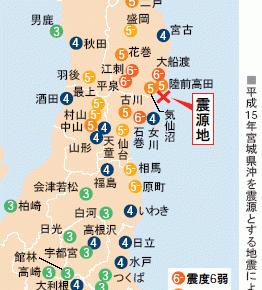
![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)