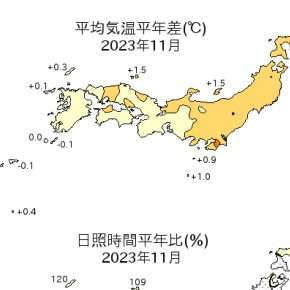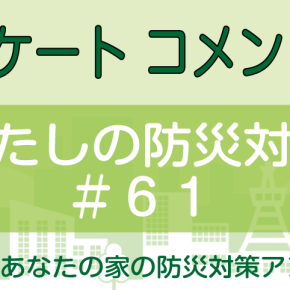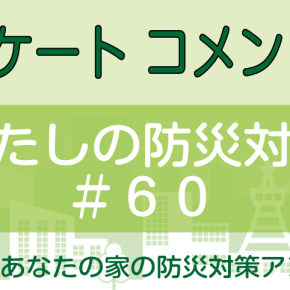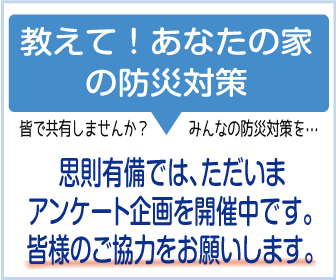今、深まる米中の対立関係は、国際政治上の大きなリスクとなっています。そして、海を隔てた隣国の中国と軍事同盟国の米国とのはざ間にある私たち日本は安全保障上の当事国ともいえます。もし台湾有事が現実となったとき、外交上の意思決定がどうなるのか、私たちは過去から学べるかもしれません。そこで今回の秋山進氏のシリーズ連載「リスクの本棚」では、冷戦時代に、米ソ両国の対立が核戦争の危機へと発展した歴史的な大事件を、それぞれの当事国の立場から緻密に分析した書籍『キューバ危機 – ミラー・イメージングの罠』を取り上げていただきました。
連載・リスクの本棚~リスクに関わる名著とともに考える~vol.14
デイヴィッド・A・ウェルチ/ドン・マントン
『 キューバ危機 ミラー・イメージングの罠 』 (2015年)
キューバ危機というのは1962年の10月、ソ連がキューバに核ミサイルを配備中であることをアメリカ軍の偵察機が発見したことから、超大国である米ソが鋭く対立し、世界が全面核戦争の一歩手前まで到達してしまったという事件である。詳しくは同事件について書いたダイヤモンドオンラインの記事を見てほしいのだが、この記事を書くために調べていく中で、もっとも印象的であった著作として「キューバ危機 ミラー・イメージングの罠」を本連載にて紹介したいと思う。
 キューバ危機 ミラー・イメージングの罠 (中央公論新社) |
この本では、「決定の本質」で展開されている分析のうち、とくに国家の指導者の認識、思考、行動に焦点を当てた分析が展開されている。したがって、こちらの主役は、アメリカのケネディ大統領、ソ連のフルシチョフ第一書記兼首相、そしてキューバのカストロ議長の3人である。
重要ポイントは以下になる。
- ● アメリカ、ソ連、キューバの三か国の指導者が自らの歴史的視点や経験に深く根ざした認識・判断によって行動し、相手の経験や認識が重要な点でまったく異なるのをほぼ忘れていたこと。
- ● 三人とも勝手に自分の姿を相手に投影し、相手も自分と全く同じように世界を見ているだろうと思い込み(ミラー・イメージング)、自らの行動がいかなる結果を引き起こすか、また相手がどう反応するかを読み誤ったこと。
- ● さらには、三人の指導者は、いずれも自分たちの選択が、批判的かつ注意深く精査されることはないとの前提で行動していた。本来、自らの信条を揺るがしかねない情報をも摂取した上で政策は選択されるべきだが、ステレオタイプ(固定観念)、アフォリズム(箴言)、格言、あるいは原則的な行動基準から引き出した推論により選択が左右された。
- ● したがって、指導者は上記のような誤りに自分が陥る可能性を深く理解し、相手の歴史的視点や経験、認識や判断に対して「共感」を寄せて発言し行動をするが重要である。
ということになる。

ケネディ大統領* 、 フルシチョフ第一書記 、 カストロ議長
*photo by History in HD @historyhd ,unsplash.
実際のところ、ミサイル基地の建設が早期に発見されるリスクをフルシチョフが過小評価したのは、ミラー・イメージング、希望的観測、意図的怠慢が理由だった。こういった態度の根底には、秘密配備が失敗するはずがないという、一か八かの独りよがりの心理があった。そして、アメリカ政治をじかに観察しているソ連の情報機関の意見を聴くこともなく、計画に疑問を抱く者たちを黙らせ、イエスマンと無能な者で脇を固めた。
ケネディは、フルシチョフが危険をおかしてでもミサイルをキューバに持ち込むとの可能性を過小評価した、というのも、そうした賭けがフルシチョフにとって魅力的であるとは想像できなかったか、あるいは、たとえフルシチョフがそう思ったところで、彼自身の行動によりケネディがどれほど難しい立場に置かれることになるか見誤るはずはあるまいと考えたからである。ただ、この考えはケネディ大統領だけのものではなかった。政権の中枢でソ連が核ミサイル配備を試みうると考えた者はマコーンCIA長官ただ一人であった。ほぼ全員が、フルシチョフがやりそうなことについて、おそろしいほどの見当ちがいをしていたのである。
カストロは、アメリカは自国の玄関口にある事実上の元植民地で社会主義体制が成立することは容認できるはずはないと考えていた。そこで、自国の情報コミュニティがアメリカのキューバ侵攻の可能性は低いと評価していたにも関わらず、それを無視した。そして、キューバの地にソ連の核兵器を設置すれば、史上初めて、キューバは宿敵アメリカと同等に渡りあえるようになるだろうと信じた。ミサイル配備により彼のプライドは満たされたし、キューバが長らく耐え忍んできたアメリカに対する屈辱の歴史をうめあわせるチャンスが生じたと考えたのである。
彼らはみな他者が自分と違う視点や経験を持っていることを忘れていた。自らがすでに持っていた信念に反する情報には心を開かなかったし、そういう情報を求めもしなかったのである。
これらのことから、著者が強調するのは、「相手に対して共感する努力をしないと破滅的な結果を招きかねない」ということである。キューバ危機においては、事態が制御不能になる寸前に、ケネディとフルシチョフがお互いを理解すべく努力し、平和的解決を図ろうという「共感」を示したことによって、問題解決の道筋が開かれた。実際のやり取りでは、相手の立場をおもんばかり、振り上げたこぶしをおろすことができる名目や時間的猶予を与えるといったことも行われたのである。
もしケネディがフルシチョフに対する共感のないまま、当初の怒りに任せて、海兵隊によるキューバ侵攻を行ったら、どうなったであろうか。CIAは当初キューバに4000人から5000人規模のソ連軍部隊がいると考えていた。そして侵攻準備直前では8000人~12000人と見積もっていたのだが、本当は42000人いた。しかもソ連軍は戦術核兵器で武装していた。したがってもし本当に侵攻していたら、上陸前後に海兵隊は瞬間的に抹殺されてしまっていた可能性が高い。そうなったら、米国内の怒り狂う世論におされて、そのまま世界全面核戦争が勃発しただろう。二人の指導者が、最後の最後の段階でどうにか培った「共感」によって世界は救われたのだった。
●学ばれない教訓
本書では、このように別の立場にあって、別の視点を持つ他者に対する「共感」の重要性が語られるのだが、このように重要な教訓が、歴史的には少しも学ばれない傾向にあることも記されている。
教訓のうちもっとも重要なものは、おそらくもっとも古くからの教訓である。すなわち、大国は小国の要求や欲望、ものの見方を無視して、自分たちも危ない目にあうというものである。19世紀と20世紀にキューバがつよく求めたものに対してアメリカが示した無神経さが、キューバ危機の根っこにあった。ヴェトナムが強く求めた者に対してアメリカが無神経だったために、東南アジアは大混乱に陥った。ソ連はアフガニスタンでソ連版のヴェトナム戦争に迷い込んだ。79年から89年まで、戦い抜く覚悟を決めていた反植民地主義勢力の抵抗する闘争により、およそ1万5千人のソ連人とともに100万人以降のアフガン人が命を失った。しかし、もしかするともっとも重大な犠牲者はソ連そのものだったかもしれない。打ちひしがれ、血を流し、もはや世界における自らの地位にも使命にも確信がもてなくなったソビエト社会主義共和国連邦は、91年、変化を求める内外からの圧力が強まるのを前に、統一を維持する能力も意思も喪失してしまった。
本書では、もしケネディが暗殺(1963年11月)されず、フルシチョフが失脚(1964年10月)せず、米ソ超大国の指導者が互いに共感を継続的に維持しておれば、世界はもう少し希望に満ちたものになった可能性があったことが語られている。しかし残念ながらそうはならなかった。そして残された者たちは、この事件から一定程度、「共感」の重要性を学んだが、多くはさらに別のものを学んだのだった。
ケネディのあとを継いだリンドン・ジョンソン(キューバ危機当時は副大統領)は超大国の関係を安定させることの重要性を理解しそのことに留意したが、キューバ紛争からより多く学んだのは、注意深く軍事力を利用すればアメリカの国益に資するということだった。そして、ヴェトナム戦争の敵は国際共産主義だと考え、本当の敵が、ヴェトナム人が自国の解放と統一のために戦おうとするナショナリズムだということがわからずに戦争を泥沼化させた。ヴェトナムの敵や人民に対する共感がなかったからである。
ケネディ大統領の弟であり、当時の司法長官のロバート・ケネディはキューバ危機について「13日間――キューバ危機回顧録(1969年)」を著した。この本の草稿の写しを事前に読んだ有力助言者オドネルにロバートが感想を求めると、「とても面白かったよ、ボビー。でも君のお兄さんもキューバ危機の解決に何がしかの関係があると思っていたんだが」と述べると、ロバートは「でも、兄は今年の大統領選に出馬しませんからね」と答えたという。キューバ危機の体験を、自らが大統領になるための宣伝に使おうと試みたのである。(そして彼は1968年選挙運動中に暗殺される)
そしてカストロである。カストロは米ソの指導者が「共感」によって和解の道を探り始めた際にも、他の二人に歩み寄ることはなかった。そして、ソ連がこの件で、キューバの立場を配慮することなく、勝手にミサイルの撤退を意思決定したことを決して許そうとはしなかった。(アメリカの侵攻が事実上なくなったにもかかわらず)またアメリカが自立した社会主義国キューバを受け容れることはないとも固く信じていた。ただ感情的には頑固であっても、カストロは非常に頭が切れた。そして実利主義的能力にあふれていた。彼はキューバ危機を対ソ関係に利用し、毎年後ろ盾としてのソ連から何十億ドルにも相当する軍事・経済援助を搾り取ったのである。国際的危機とその顛末が小国の利益につながることを証明したのであった。しかし、その後、最終的には当時世界がどれだけ深い危機の中にあったかを理解し、世界の他国に対して「共感」の姿勢の重要性を語ることもあった。ただそれは、病気による危篤状態から回復した2010年のことである。50年近くの年月が流れていた。
さて、現在、かつてのパワーバランスが崩れ、世界中の緊張が高まりつつある。大国は大国の論理を振りかざし大国間での緊張を高めている。そのさなかで小国は生き残りをかけた戦略を実行し、その際には大国との関係をしたたかに使おうとする国家もある。こんな状況下であっても、著者が言うように、もし多くの指導者が、相手国や相手国の指導者に対して「共感」を示すことができるのであれば、世界は破滅することなく続いていくのだろう。しかしながら、これまた本書が言うように、人類も指導者たちもなかなか「共感」の重要性を学べない。「もう2度とキューバ危機のようなことは起こらない」とは誰も言い切れないだろうし、その可能性は着実に高まっているのである。
評者:秋山 進(あきやま・すすむ)

1963年、奈良県生まれ。京都大学経済学部卒。リクルート入社後、事業企画に携わる。独立後、経営・組織コンサルタントとして、各種業界のトップ企業など様々な団体のCEO補佐、事業構造改革、経営理念の策定などの業務に従事。現在は、経営リスク診断をベースに、組織設計、事業継続計画、コンプライアンス、サーベイ開発、エグゼクティブコーチング、人材育成などを提供するプリンシプル・コンサルティング・グループの代表を務める。国際大学GLOCOM客員研究員。麹町アカデミア学頭。
主な著書に『「一体感」が会社を潰す』(PHP研究所)、『それでも不祥事は起こる』『転職後、最初の1年にやるべきこと』(日本能率協会マネジメントセンター)、『社長!それは「法律」問題です』(日本経済新聞出版)などがある。
【関連リンク】
・プリンシプル・コンサルティング・グループ:https://www.principlegr.com/
・麹町アカデミア:http://k-academia.co.jp/
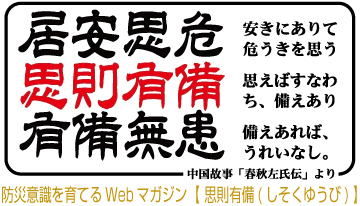






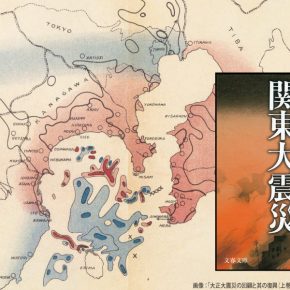












![宮本常一「春一番」の由来と歴史と名言(1907~1981 / 「春一番」を最初に報告した民俗学者 離島研究の創始者)[今週の防災格言777] 宮本常一「春一番」の由来と歴史と名言(1907~1981 / 「春一番」を最初に報告した民俗学者 離島研究の創始者)[今週の防災格言777]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/02/68c1fc75df853eec3aa5d1f9f6f60925-290x290.jpg)

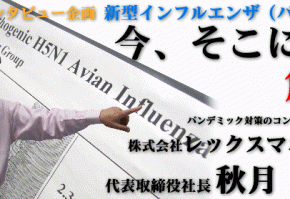
![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)