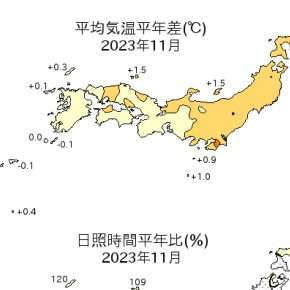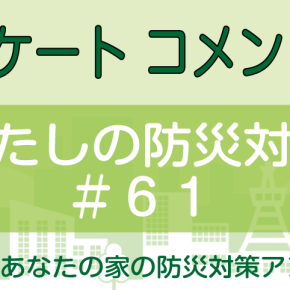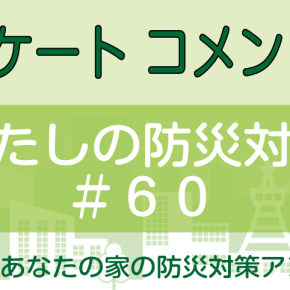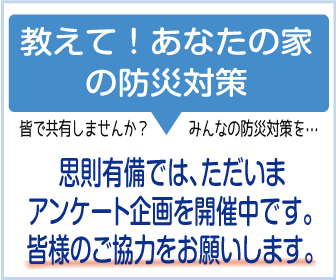遥か昔、古代ギリシャ時代。新興国アテネと覇権国スパルタとのあいだで発生した戦争(紀元前431年から紀元前404年)を、古代アテネの歴史家トゥキディデスは「戦史(ペロポネソス戦争の歴史)」としてまとめました。それから2500年の後、政治学者グレアム・アリソン氏は、新興国と覇権国とが戦争に行きつくまでのジレンマを「トゥキディデスの罠」と命名して、米中戦争へと至る可能性について警鐘を鳴らしました。秋山進氏のシリーズ連載「リスクの本棚」の第10回は、2017年のアリソン氏の著書『米中戦争前夜―新旧大国を衝突させる歴史の法則と回避のシナリオ』を取り上げていただきました。
連載・リスクの本棚~リスクに関わる名著とともに考える~vol.10
グレアム・アリソン『 米中戦争前夜 -新旧大国を衝突させる歴史の法則と回避のシナリオ- 』(2017年)
■ “米中戦争の可能性は、ただ「ある」というだけでなく、考えられているよりも非常に高い。”(本文より)
ハーバード大学ケネディ行政大学院の初代学長であり、歴代国防長官の顧問をつとめたグレアム・アリソン氏の2017年の著作です。アリソン教授といえば、キューバ危機時のケネディ政権の意思決定のあり方を分析した「決定の本質 キューバ・ミサイル危機の分析(中央公論新社、日経BP社)があまりにも有名で、そこで提示された意思決定における3つのモデル(通称アリソン・モデル)は、あらゆる意思決定の分析に大きく役立ちます。
 米中戦争前夜(ダイヤモンド社) |
そして本書、「米中戦争前夜」(原著 DESTINED FOR WAR)は、過去500年の歴史をさかのぼって「新興国が覇権国の地位を脅かしたケース」を分析し、そこから得られた知見を現在の米中関係に当てはめて論考した快著です。思考のスケールの大きさと中核となるコンセプトの明確さが印象的で、さらには現状への的確な適用がなされているため高い説得力をもちます。
■ 「トゥキティディスの罠」とは何か
まず、本書の中核のコンセプトである「トゥキティディスの罠」を簡単に説明しましょう。
トゥキティディスの罠とは、「新興国が覇権国に取って代わろうしたときに国際関係に構造的ストレスが生じて、暴力的な衝突が起きうること」を言います。過去500年の間にそのような状況は16回あり、そのうち12回が戦争に至りました。トゥキティディスは、『戦史(ペロポネソス戦争の歴史)』で、覇権国スパルタ対新興国アテネについて記した紀元前5世紀の歴史家の名前です。
アリソン教授によると、新興国と覇権国が戦争に至る道筋は以下のようになります。
アテネとスパルタの指導者は、戦争を回避するために最大限の努力をしたが、国内がじりじりと戦争に傾いていくのを止めることはできなかった。どちらも相手と駆け引きしながら、戦わないのは不名誉であり破滅的だと考える国内の政治勢力にも対応しなければならなかった。
これこそDESTINED FOR WAR(運命づけられた戦争)といえましょう。両方とも本当は戦争などしたくないのに、結果として戦争をすることになってしまうのです。
「いやいや、それは昔の話だ。政治家はそこまでバカではないし、国民は賢くなった。そもそも今はあらゆる情報を獲得できる時代になっている。だから、トゥキティディスの罠は抑止されるはず」という人もいるかもしれません。それに対してアリソン教授は、
経済戦争が核戦争に発展するわけがないと思う読者は、日本とアメリカが真珠湾にいたった興味深い道のりをよく見つめるべきだ。国内の結束を図るために、外国に自国を攻撃させるなんてありえないと思うなら、ビスマルクを思い出すといい。海上での競争が国家間の戦争に発展する可能性を考えるなら、イギリスとオランダの関係が手掛かりになるだろう。
と、戦争は実際に起こりうることを歴史から説明します。
■ 中国はかつてのアメリカと同じだ。
アメリカもかつては新興国でした。そして覇権国イギリスにとって代わろうとして大きな摩擦を起こしたのです。アリソン教授は、現在の米中の関係は、1900年セオドア・ルーズベルト大統領時代の英米関係に似ていると言います。
「外国と平和な関係を維持したいなら、究極的には、人間の分別がもたらす仲裁協定よりも、一流の戦艦からなる一流の艦隊を頼りにするほうが賢いというものだ。」
今後「文明社会の結束を弱めるような、慢性的な不正行為や無気力は、アメリカであろうと他の場所であろうと、究極的には文明国家の介入を必要とするだろう。また西半球でそのような不正行為や無気力が目に余る場合は、アメリカはモンロー主義を堅持するために、いかに不本意であっても国際的な警察権を行使せざるをえない」
当時アメリカは、経済的、軍事的に力をつけ、米西戦争で勝利し、プエルトリコ、グァム、フィリピンを獲得しました。そして西半球はわが物だという意識を強くし、さらには、パナマをコロンビアから独立させ、運河の権益を獲得・・・とアメリカの行動は、世界からは、現状変更を進める挑戦国と見られたようです。セオドア・ルーズベルトは、「アメリカのパワーを世界の舞台に意欲的に誇示した最初の大統領でした。
そして、このとき覇権国であった英国は、本国がドイツの脅威にさらされていたこともあって、米の要求を呑み、西半球から撤退したのでした。
では、イギリスと同じようにアメリカがアジアから撤退するような可能性はあるのでしょうか?アリソン教授は以下のように言います。
アメリカが当時のイギリスと同じ運命を受け入れる兆しはほとんどない。
■ 米中の軍事力、経済力はすでに拮抗している。
中国の躍進はいうまでもありませんが、すでに経済力だけでなく、軍事力においても米中は拮抗してきています。購買力平価でみると米中のGDPはすでに同等になっています。アジア地域の軍事バランスは、台湾問題では通常兵器の9領域中6つ、南シナ海では9領域中4領域ですでにアメリカよりも中国が優位または同等といいます。(ランド研究所)よって米空母も中国の1600㎞以内には入れないし、宇宙においては米の軍事衛星も中国によって妨害される状況にあるのです。
この躍進をリードしているのは習近平氏です。彼はいま中国をどのような方向に導いていこうとしているのでしょうか。
習は、中国が奇跡的な経済成長を維持し、市民の愛国意識を高め、国際社会でいかなる大国にもペコペコしないことで、三つの願望すべてを実現できるという圧倒的自信をもつ。そんな途方もなく巨大な野心に、ほとんどの専門家は懐疑的な見方をするが、リー(※評者註:シンガポール建国の父リー・クワンユーのこと)も私も、習が失敗するほうに賭けるつもりはない。リーが言ったように、「再び覚醒した『運命』という感覚には強烈なパワーがある」からだ。
中国の「運命」とは、「中国を再び偉大な国にする」ことになります。具体的には
・中国を西洋列強がやってくる前のアジアの覇権国に復活させること
・グレーターチャイナ(大中華圏)の支配権を取り戻すこと。これには新疆やチベットだけでなく、香港と台湾が含まれる。
・国境および隣接地域に歴史的な影響圏を復活させ、歴史上の偉大な国々のように周辺国を服従させること
・国際機構で他の国々から敬意を払われること
です。
こうした野望の中核には、中国を世界の中心と見なす中華文明の伝統的な考え方がある。中国語で中国とは、「真ん中にある王国」という意味だ。「真ん中にある」とは、対立する国々の中心という意味ではなく、天と地のすべての中心という意味だ。
しかし、この野望を達成するためには、強権的で私権を制限する意思決定が行われることもあります。これに対して、国民から大きな反発が出るはずだ、と米国人は考えるでしょう。しかし、そういう米国的な発想は必ずしも中国国民には当てはまらないと言います。その理由は
アメリカの建国の父たちは、権威に対して強い不信感を抱きつつ、社会には政府が必要だと考えた。 ・・・(中略)・・・ 中国人の政府と、その社会における役割に対する見方は、ほどんど正反対だ。歴史は中国人に、何より重要なのは秩序であり、その秩序を実現するには政府が不可欠だと教えた。「中国の歴史と文化を見ると、中央(北京または南京)が強力なときは、国全体が豊かなことが分かる。中央が弱いと、省や群が小さな軍閥に支配される」とリー・クワンユーは指摘した。したがって、アメリカ人が必要悪と見なす強力な中央政府は、中国人にとっては国内外で秩序と公益を高まる重要な機構だ。
この考え方によると、強権的な政府だからといって、国民に支援されないわけではないということになります。
■ 戦争は不可避ではないが、かなりの確率で起こってしまう。
そのうえで、アリソン教授は、現代の中国が世界にもたらせているような、急速かつ地殻変動的なパワーシフトは、歴史上に例がないと言います。
そして戦争に至る5つのシナリオを提示します。
それは、偶発、台湾の独立、第三者の挑発(例 尖閣問題)、北朝鮮の崩壊、経済戦争のエスカレート、です。これらはいずれも現実に起こりうるでしょう。そして、それらへのアメリカの対応策として、適応(状況を受け入れる)、中国の弱体化、長期的交渉、米中関係の再定義、が語られます。大変示唆に富むので、興味を持たれた方はぜひ本書を読んでいただきたいと思います。
最後に、この分析を終えたアリソン教授が、米中戦争の可能性についてどう考えているかについて、記しておきます。
現在の軌道では、数十年以内に米中戦争が起こりうる可能性は、ただ「ある」というだけでなく、現在考えられているよりも非常に高い。
本書が著された2017年以降も米中関係は悪化の一途をたどっています。DESTINED FOR WAR(運命づけられた戦争)になるかもしれない米中戦争が起これば、日本や日本国民が影響を被らないことは絶対にありません。そのような状況が近づいてきていることを理解し、できる準備をしっかりとしておく必要があると考えられます。
評者:秋山 進(あきやま・すすむ)

1963年、奈良県生まれ。京都大学経済学部卒。リクルート入社後、事業企画に携わる。独立後、経営・組織コンサルタントとして、各種業界のトップ企業など様々な団体のCEO補佐、事業構造改革、経営理念の策定などの業務に従事。現在は、経営リスク診断をベースに、組織設計、事業継続計画、コンプライアンス、サーベイ開発、エグゼクティブコーチング、人材育成などを提供するプリンシプル・コンサルティング・グループの代表を務める。国際大学GLOCOM客員研究員。麹町アカデミア学頭。
主な著書に『「一体感」が会社を潰す』(PHP研究所)、『それでも不祥事は起こる』『転職後、最初の1年にやるべきこと』(日本能率協会マネジメントセンター)、『社長!それは「法律」問題です』(日本経済新聞出版)などがある。
【関連リンク】
・プリンシプル・コンサルティング・グループ:https://www.principlegr.com/
・麹町アカデミア:http://k-academia.co.jp/
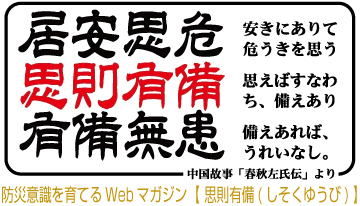







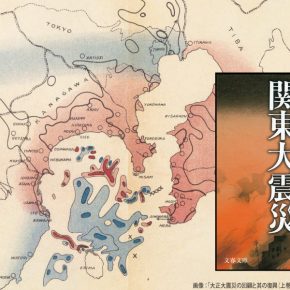













![口永良部島噴火の時、中央気象台鹿児島測候所の報告書に書かれた格言[今週の防災格言389] 口永良部島噴火の時、中央気象台鹿児島測候所の報告書に書かれた格言[今週の防災格言389]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/204-290x290.png)
![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)