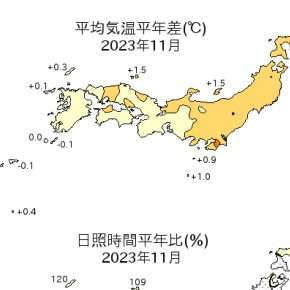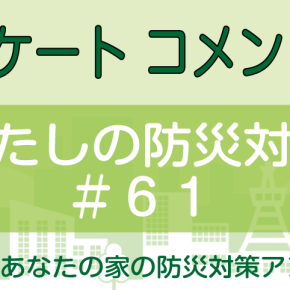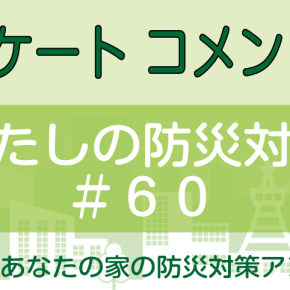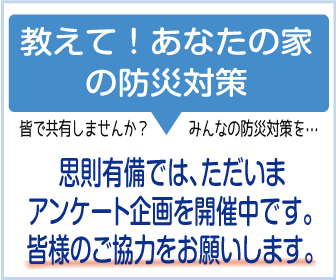数多くの企業経営リスク分析に関わってこられた秋山進氏(プリンシプル・コンサルティング・グループ代表)にリスクにかかわる名著を要約いただくシリーズ連載「リスクの本棚」の第二回は、東大安田講堂事件や連合赤軍によるあさま山荘事件という歴史的な事件現場の指揮を経験され、1980年代初期からテロや大規模災害への備えとして日本の国家危機管理システムの整備の必要性を訴え続けた元警察官僚で作家の佐々淳行氏を取り上げていただきました。
連載・リスクの本棚~リスクに関わる名著とともに考える~vol.2
“平時の能吏”ではなく“乱世の雄”に指揮官をまかせよ! ~公助よりも、互助(共助)自助を~
佐々淳行『重大事件に学ぶ「危機管理」』(2004年)
◆著者は初代内閣危機管理室長
「リスクの本棚」第二回は、初代の内閣危機管理室長で ”危機管理を日本語にした” ことでも知られる佐々淳行氏の「重大事件に学ぶ「危機管理」」を取り上げる。
著者による「完本 危機管理のノウハウ」(文藝春秋)は、あさま山荘事件をはじめ警察幹部としての豊富な経験をもとにした危機管理のもっとも優れた教科書であり、究極の状況下において組織と人をいかに動かすかというマネジメントの佳作でもある。残念なことに佐々氏の著作は今やその多くを古書(kindleで読める著書もある、本書はその一つ)として読むしかないが、この領域に関係する人にとっては必読者といえる。今回は、完本 危機管理のノウハウの要約版ともいえる本書をもとに佐々氏の考えを紹介したい。
 重大事件に学ぶ「危機管理」(文春文庫) |
本書に入る前に認識しておきたいことは、危機管理(クライシスマネジメント)とリスクマネジメントの関係性である。一般的に、危機管理は、リスクマネジメントの1つの領域と考えられる。リスクマネジメントがまだ起こっていないすべての事象をカバーするのに対して、危機管理は、重大事件・事故が起こることを前提に、実際の場面でどのように対応するか、ダメージをいかに少なくするかというアクション領域を主に論じるものである。
危機管理は、さらに細かくわけるとクライシスマネジメント(危機管理)、インシデントマネジメント(事件処理)、アクシデントマネジメント(事故処理)の三段階があるのだが、事件処理、事故処理は、予想外ではあったとはしても、国家や組織の根幹を揺るがすほどの影響力はない。一方、クライシスマネジメント(危機管理)はその扱いに失敗すると国家や組織を危急存亡の秋に陥れてしまう。
◆危機を表すABCDEF
では、ここでいう危機にはどのようなものがあるのか。著者は英語の頭文字を使ってABCDEFを認識すべきと言っている。
-
A アトミック(原子力)
B バイオロジー(生物〈兵器〉)
C ケミストリー(化学〈兵器〉)、コンピュータ、カルト
D ディザスター(災害)
E エコノミー(経済)
F ファイナンス(金融)
この本が出版されたのは2004年のことであるが、その後も、これらの危機が顕在化している。
Aのアトミックは、言うまでもないが2011年の福島第一原発の事故がある。
Bのバイオロジーは、いまのところ、そうではないという説が有力であるが、新型コロナウィルスに際して生物兵器説が飛び交った。過去には炭疽菌テロもあった。
Cのケミカルは、オウム真理教によるサリン等の化学兵器が記憶に新しい。今後もカルト集団や他国の攻撃などにさらされる可能性はある。コンピュータに関しては、日々ハッキングが繰り返されており、サイバー空間の戦争は日常のこととなっている。サイバーテロへの対応に失敗すると立ち直れないほどのダメージを受ける。
D ディザスターは、東日本大震災だけでなく、毎年、100年に一度といった大きな台風、風水害が日本を襲ってくる。これらの自然災害の状況は悪化こそすれ和らぐ気配はない。
EとF エコノミーとファイナンス。経済危機と金融危機は不即不離の関係にあるが、2008年のリーマンショックという金融危機は、日本経済を一時大きな危機に追い込んだ。そして2020年後半以降は、コロナ後の経済危機が社会を覆うだろう。
このように、代表的な危機について簡単に述べてみたが、我々はあまりの危機の多さに一種の不感症になっているかもしれない。これらの危機は一つひとつがたいへん大きな破壊力をもっており、その一つひとつに確実に対応しなければ、国家や組織は実際に厳しい状況に陥ることになってしまう。
◆クライシスの際に判断をまかせられる指揮官が必要
佐々氏は、迫りくるこれらの危機に対して、社会全体が今までのやり方を大きく変えていく必要があると述べている。
まず指摘するのは、どんな人を指揮官に選ぶかということである。
著者は、自分が見てきたたくさんの経験から、平時に優秀な人の多くが危機時にはまったく役に立たないことを指摘する。曰く、「平時の能吏、乱世の雄」であり、非常時においては、平時にはトラブルメーカーとして忌避されるような“乱世の雄”が指揮官にならなければいけないという。
というのは、平時の組織が力を発揮する条件は、1 リードタイムが十分にある 2 きちんと成文化されたルールが定まっている 3 予算がついている 4 任務分担が決まっている、の4つであり、これらの条件下にあって、きっちりと人と組織を動かしていくのが平時の能吏の得意とするところである。しかしながら、危機下にあっては、平時の4条件のうち1つすらも該当しないのだ。そして、そのような不確定の状況下にあっても果敢に動き、意思決定し、組織を動かすことのできる人材とは、能吏とは違った意識と行動様式を持っているという。
具体的には、「オレがやらずに誰がやる」という使命感を持つ人、「何になったか」ではなく「何をなしたか」を重要に考える人、人にやらせるだけではなく、自分の手を汚す人(自ら動く人)である。何が重要かを、時間がない中で瞬時に判断し、不完全な情報しかないなかで、経験にもとづく勘と知性を総動員して、いま何をやることが大事かを考え、かつ果敢に意思決定し、人を鼓舞する人である。
一方、著者が、その対極にある人として、危機下に役に立たない人として指摘するのは、“すぐに会議を開こうとする人”である。
著者は「会議好きにロクな奴はいない」と喝破したうえで、1986年に起こった伊豆大島の三宅島の209年ぶりの大噴火の際の状況を語る。管轄である国土交通省は、迫りくる危機にも関わらず、省内に籠って会議ばかりしていて何も動かない。これでは1万3000人の命が危ないと考えた内閣(具体的には後藤田官房長官と中曽根総理大臣)が総理命令として、佐々氏に前例のない権限を与えて、海上自衛隊と海上保安庁の艦船、民間のフェリーなどを大島に急行させ1万3000人を脱出させた。国土交通省の会議が終わった午後11時45分には、救出作戦はあらかた終了していたという。評者はこの事件を覚えている。自衛隊の大きな艦船が島に到着したときに見せた、島民たちの「これで助かった」という安堵の顔を忘れることはできない。
なぜ緊急時に会議をしてしまうのかについて、著者は、日本人が農耕民族であり、人格円満で、敵がいなくて調整力がすぐれている人を指揮官に選ぶことを理由としてあげている。このような指揮官は、非常時においても平時と同じ行動様式を実行してしまうのだ。
ただ、組織の歴史を見るならば、いつも非常時というわけでもない。基本的には平時の期間のほうが長い(最近は、ずっと非常時のようにも思われるが)のだ。そこで、組織としては、平時の能吏を8割くらい育成し、一方で、乱世の雄は2割くらいを維持するようにすることを著者は提案している。そして、平時が続いても、乱世の雄を絶やさぬようにしておくことが重要だと説く。
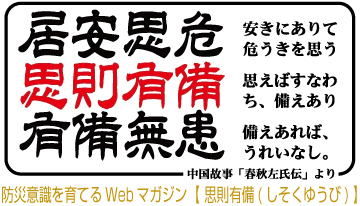
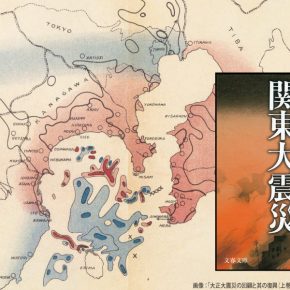
![溝上恵が読売新聞のインタビュー(1993年)で遺した名言(1936~2010 / 地震学者 東京大学地震研究所教授)[今週の防災格言145] 溝上恵が読売新聞のインタビュー(1993年)で遺した名言(1936~2010 / 地震学者 東京大学地震研究所教授)[今週の防災格言145]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2010/08/14e3e0ed4cbc4c114b79d555180e9266-290x290.jpg)

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)