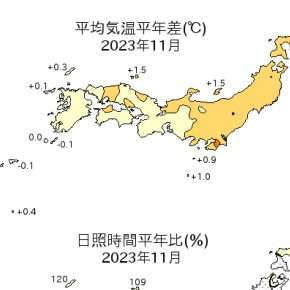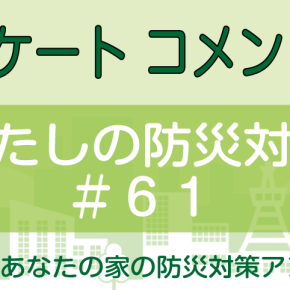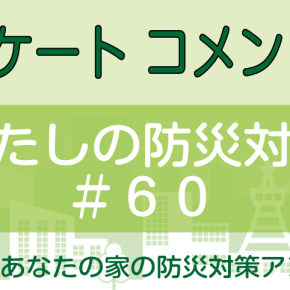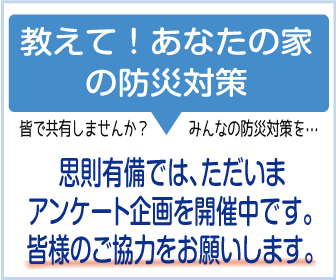![高村薫が毎日新聞に寄稿した『恐怖が心に穴をあけた』に残した格言[今週の防災格言294]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/bousaikakugen.jpg)
『 どうにかして生きていくのも、最後は自分の力でしかない 』
高村 薫(たかむら かおる)女史は、大阪府大阪市生まれ、吹田市在住の作家。1975(昭和50)年、国際基督教大学 (ICU) フランス語専攻卒。外資系商社勤務を経て、1990(平成2)年『黄金を抱いて翔べ』で第3回日本推理サスペンス大賞を受け作家デビュー。1993(平成5)年『リヴィエラを撃て』で第6回山本周五郎賞候補、第46回日本推理作家協会賞長編部門受賞。同年『マークスの山』で第109回直木賞受賞。1997(平成9)年『レディ・ジョーカー』で毎日出版文化賞。2010(平成22)年『太陽を曳く馬』で第61回読売文学賞受賞。
この格言は毎日新聞夕刊(1995年2月24日)への寄稿文『恐怖が心に穴をあけた』より。
曰く―――。
少し時間を置いたとき、当初の恐怖も失意も悲しみも、やがてさらに深い思いの中に呑みこまれていくのではないかと思う。
死生観という安易な言葉でくくることはしたくないが、要するに誰もが多かれ少なかれ人間の生き死にを考え、それぞれに言葉を失う時間をもったということである。もう立ち上がる元気もない人はもちろん、力強く明るく心を保っている人も、何くわぬ顔をしている人も、みな心にそれぞれの深い思いの穴があいている。そこから、一人一人の内なる言葉が新たに湧いてくる。
わたくしはそれを幸とも不幸とも言わないし、他人には「放っといてくれ」と言いたい。これをバネにして強く生きるのも、打ちのめされたままぼうっとしているのも、悪鬼のようになるのも、それぞれの人にとっての心の必然だし、どうにかして生きていくのも、最後は自分の力でしかないからだ。
だからこそ、動きたくても動けないお年寄りや病身の人といった、生きる権利を自分で守れない人に対する支援や保護は、何を置いても優先してほしいと切実に思う。
<中略>
失意や悲嘆の部分では、わたくしは被災者に比べて絶対的に小さいが、それでも、生まれ育った地域の懐かしい風景を、二度と見ることはないという恐ろしい喪失感はある。
また、自分自身の生業についての懐疑も、しばらくは拭えないほど大きかった。震災を前にして、小説など、トイレットペーパーほどの価値もない。被災者の心を癒すような作品を自分が書いているかというと、これもまったくそうではない。しかし、この懐疑はわたくし自身の勝手な呟(つぶや)きであるから、どうか放っておいていただきたい。物を書くという行為はわたくしの場合、物を考えるという行為と等しいので、これからはこれまで以上に、いやでも物を書きつつ考えていくしかない。地震のひと揺れで自分の中にあいた穴を、人の役に立とうが立つまいが見つめていくのは、わたくし個人の今の必然である。
■「高村薫」女史に関連する防災格言内の記事
映画監督・山田洋次(2010.5.24 防災格言)
政治家・小沢一郎(2010.01.25 防災格言)
防災格言,格言集,名言集,格言,名言,諺,哲学,思想,人生,癒し,豆知識,防災,災害,火事,震災,地震,危機管理,防災グッヅ
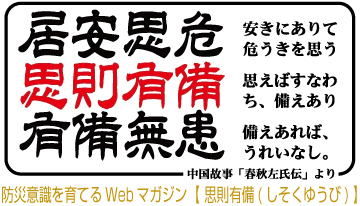
![ニッコロ・マキャヴェッリ(1469~1527 / 中世イタリア・フィレンツェ共和国の政治思想家 「君主論」著者)『戦略論』の名言 [今週の防災格言647] ニッコロ・マキャヴェッリ(1469~1527 / 中世イタリア・フィレンツェ共和国の政治思想家 「君主論」著者)『戦略論』の名言 [今週の防災格言647]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2020/05/ec5c5d5b1a0e020213343c2dde5616a2-290x290.png)
![池端清一が阪神淡路大震災で遺した名言(1929~2007 / 阪神淡路大震災時の国土庁長官(第27代))[今週の防災格言8] 池端清一が阪神淡路大震災で遺した名言(1929~2007 / 阪神淡路大震災時の国土庁長官(第27代))[今週の防災格言8]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2008/01/4b4488c805c3d2543d3896194e479956-290x290.png)
![鴨長明が「方丈記」にしるした京都地震(1185年)の名言(1155~1216 / 平安時代末期の歌人・随筆家)[今週の防災格言20] 鴨長明が「方丈記」にしるした京都地震(1185年)の名言(1155~1216 / 平安時代末期の歌人・随筆家)[今週の防災格言20]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2008/03/b16222e546cd6a566a9051eef338c361-290x290.png)
![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)
![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)
![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)